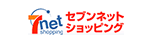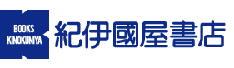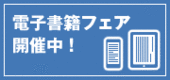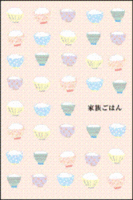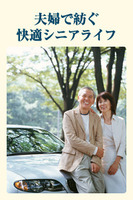言語とこころ
心理言語学の世界を探検する

| 著者 | 重野 純 編 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 教養・読みもの |
| 出版年月日 | 2010/04/05 |
| ISBN | 9784788511965 |
| 判型・ページ数 | A5・288ページ |
| 定価 | 本体2,800円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
言語とこころとは切っても切り離せない。動物のコミュニケーションやジェスチャー,思考や子どもの言語獲得,外国語,認知モデル,失語症など,心理言語学の幅広い領域を読者とともに探検しながら,言語とこころの関係を探る清新な入門テキスト。
◆目次
まえがき
第1章 心理言語学へのアプローチ
1―1 心理言語学の誕生
1―2 心理言語学の発展
1―3 心理言語学と言語心理学
1―4 主要な研究テーマ
1―5 心理言語学の未来
【さらに読み進めたい人へ】
第2章 動物のコミュニケーション
2―1 動物は「ことば」をもつのか その研究史と研究意義
2―2 原始動物の生得的コミュニケーション
2―2―1 魚類
2―2―2 昆虫
2―3 哺乳類の音声
2―3―1 哺乳類の音声にみる信号発信の意図性
2―3―2 ジリスの警戒音
2―3―3 霊長類の警戒音―意味の起源
2―3―4 霊長類以外の哺乳類がもつ警戒音の意味
2―3―5 言語的性質と非言語的性質をあわせもつ動物の音声
2―3―6 警戒音の発達的側面
2―4 動物のカテゴリー知覚
2―4―1 言語音
2―4―2 カテゴリカルな霊長類の音声レパートリー
2―4―3 動物の音声
2―5 大型類人猿の視覚言語習得
2―5―1 手話を用いた初期の研究
2―5―2 幾何図形を使ったプロジェクト
2―6 動物のコミュニケーションとその基盤となる能力に関する近年の研究動向
2―7 動物の「ことば」の研究の今後
【さらに読み進めたい人へ】
第3章 言語と思考
3―1 言語と思考に関する研究の流れ
3―2 対人的思考
3―2―1 敬語使用の戦略
3―2―2 説明の進行パターン
3―2―3 具体の科学
3―3 帰納的思考
3―3―1 カテゴリー判断
3―3―2 類似性判断
3―3―3 確率判断
3―4 演繹的思考
3―4―1 言語心像バイアス
3―4―2 注意の方向付け
3―5 おわりに,そして今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第4章 子どもの言語獲得
4―1 言語獲得研究の歴史
4―2 音声知覚の発達
4―2―1 言語のリズムをつかむ
4―2―2 単語を聴き取る
4―3 単語の学習
4―3―1 最初の試行錯誤と語彙爆発
4―3―2 さまざまな種類の単語の学習
4―4 文法の獲得
4―4―1 子どもの発話の発達的変化
4―4―2 文法的はたらきに応じた単語の分類
4―4―3 文を構成するルールの理解
4―5 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第5章 第二言語習得
5―1 第二言語習得研究の流れ
5―1―1 第二言語とは
5―1―2 獲得・習得・学習
5―1―3 研究の誕生と発展
5―2 第二言語習得の理論モデル
5―2―1 生成文法にもとづくモデル
5―2―2 第二言語におけるUGの利用可能性
5―2―3 初期状態についての仮説
5―2―4 認知的アプローチ
5―2―5 第二言語習得の年齢要因
5―2―6 バイリンガリズム
5―3 日英の疑問文と第二言語習得
5―3―1 疑問文
5―3―2 直接疑問文
5―3―3 間接疑問文の統語と意味
5―4 句語彙項目(PLI)の考察
5―4―1 慣用表現
5―4―2 句語彙項目(PLI)
5―5 「ここまで」と「これから」
【さらに読み進めたい人へ】
第6章 音声知覚
6―1 パターン・プレイバック装置から音声自動翻訳機まで
6―2 音声知覚の基礎
6―2―1 音韻,音素,形態素,弁別的特徴
6―2―2 フォルマント周波数と発声開始時間(VOT)
6―2―3 構音結合
6―2―4 音声的普遍性と母音の正規化
6―3 音声知覚実験と音声情報処理モデル
6―3―1 カテゴリー知覚と運動指令説
6―3―2 選択的順応効果と特徴検出モデル
6―3―3 音韻の知覚に生じる文脈効果
6―3―4 知覚的統合
6―4 パラ言語情報についての実験研究
6―5 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第7章 単語の認知
7―1 今日までの研究の流れ
7―2 音声単語認知モデル
7―2―1 ロゴジェン・モデル
7―2―2 トレース・モデル
7―2―3 コホート・モデル
7―2―4 ネイバーフッド・アクティベーション・モデル
7―3 音声単語認知過程
7―3―1 単語候補の活性化
7―3―2 単語候補間の競合
7―4 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第8章 文の構造と理解
8―1 文の理解と言語学的概念
8―2 文の構造
8―2―1 生成文法
8―2―2 変形規則
8―2―3 統語解析のモデル
8―3 文理解の個人差とワーキングメモリ
8―3―1 ワーキングメモリ容量による文理解の個人差
8―3―2 統語的複雑さの処理
8―3―3 言語的曖昧文の処理
8―3―4 語用論的処理と統語的処理の相互過程
8―4 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第9章 言語とジェスチャー
9―1 ジェスチャー研究の歴史
9―2 ジェスチャーの分類
9―3 表象的ジェスチャーの産出要因
9―3―1 聞き手要因
9―3―2 話し手要因
9―3―3 課題内容
9―4 こころ,ことば,表象的ジェスチャー
9―5 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第10章 失語症
10―1 失語症研究の流れ
10―1―1 神経心理学の誕生
10―1―2 古典論の成立
10―1―3 全体論の台頭
10―2 失語症のタイプと症状
10―3 失語症患者における文発話の障害
10―3―1 語彙範疇の障害 新造語ジャーゴン
10―3―2 日本語話者における語彙範疇の障害
10―3―3 日本語話者における機能範疇の障害
10―3―4 文の生成プロセス
10―4 脳イメージング研究と失語症
10―5 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
文 献
人名索引
事項索引
編者・執筆者紹介
装幀=虎尾 隆
まえがき
第1章 心理言語学へのアプローチ
1―1 心理言語学の誕生
1―2 心理言語学の発展
1―3 心理言語学と言語心理学
1―4 主要な研究テーマ
1―5 心理言語学の未来
【さらに読み進めたい人へ】
第2章 動物のコミュニケーション
2―1 動物は「ことば」をもつのか その研究史と研究意義
2―2 原始動物の生得的コミュニケーション
2―2―1 魚類
2―2―2 昆虫
2―3 哺乳類の音声
2―3―1 哺乳類の音声にみる信号発信の意図性
2―3―2 ジリスの警戒音
2―3―3 霊長類の警戒音―意味の起源
2―3―4 霊長類以外の哺乳類がもつ警戒音の意味
2―3―5 言語的性質と非言語的性質をあわせもつ動物の音声
2―3―6 警戒音の発達的側面
2―4 動物のカテゴリー知覚
2―4―1 言語音
2―4―2 カテゴリカルな霊長類の音声レパートリー
2―4―3 動物の音声
2―5 大型類人猿の視覚言語習得
2―5―1 手話を用いた初期の研究
2―5―2 幾何図形を使ったプロジェクト
2―6 動物のコミュニケーションとその基盤となる能力に関する近年の研究動向
2―7 動物の「ことば」の研究の今後
【さらに読み進めたい人へ】
第3章 言語と思考
3―1 言語と思考に関する研究の流れ
3―2 対人的思考
3―2―1 敬語使用の戦略
3―2―2 説明の進行パターン
3―2―3 具体の科学
3―3 帰納的思考
3―3―1 カテゴリー判断
3―3―2 類似性判断
3―3―3 確率判断
3―4 演繹的思考
3―4―1 言語心像バイアス
3―4―2 注意の方向付け
3―5 おわりに,そして今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第4章 子どもの言語獲得
4―1 言語獲得研究の歴史
4―2 音声知覚の発達
4―2―1 言語のリズムをつかむ
4―2―2 単語を聴き取る
4―3 単語の学習
4―3―1 最初の試行錯誤と語彙爆発
4―3―2 さまざまな種類の単語の学習
4―4 文法の獲得
4―4―1 子どもの発話の発達的変化
4―4―2 文法的はたらきに応じた単語の分類
4―4―3 文を構成するルールの理解
4―5 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第5章 第二言語習得
5―1 第二言語習得研究の流れ
5―1―1 第二言語とは
5―1―2 獲得・習得・学習
5―1―3 研究の誕生と発展
5―2 第二言語習得の理論モデル
5―2―1 生成文法にもとづくモデル
5―2―2 第二言語におけるUGの利用可能性
5―2―3 初期状態についての仮説
5―2―4 認知的アプローチ
5―2―5 第二言語習得の年齢要因
5―2―6 バイリンガリズム
5―3 日英の疑問文と第二言語習得
5―3―1 疑問文
5―3―2 直接疑問文
5―3―3 間接疑問文の統語と意味
5―4 句語彙項目(PLI)の考察
5―4―1 慣用表現
5―4―2 句語彙項目(PLI)
5―5 「ここまで」と「これから」
【さらに読み進めたい人へ】
第6章 音声知覚
6―1 パターン・プレイバック装置から音声自動翻訳機まで
6―2 音声知覚の基礎
6―2―1 音韻,音素,形態素,弁別的特徴
6―2―2 フォルマント周波数と発声開始時間(VOT)
6―2―3 構音結合
6―2―4 音声的普遍性と母音の正規化
6―3 音声知覚実験と音声情報処理モデル
6―3―1 カテゴリー知覚と運動指令説
6―3―2 選択的順応効果と特徴検出モデル
6―3―3 音韻の知覚に生じる文脈効果
6―3―4 知覚的統合
6―4 パラ言語情報についての実験研究
6―5 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第7章 単語の認知
7―1 今日までの研究の流れ
7―2 音声単語認知モデル
7―2―1 ロゴジェン・モデル
7―2―2 トレース・モデル
7―2―3 コホート・モデル
7―2―4 ネイバーフッド・アクティベーション・モデル
7―3 音声単語認知過程
7―3―1 単語候補の活性化
7―3―2 単語候補間の競合
7―4 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第8章 文の構造と理解
8―1 文の理解と言語学的概念
8―2 文の構造
8―2―1 生成文法
8―2―2 変形規則
8―2―3 統語解析のモデル
8―3 文理解の個人差とワーキングメモリ
8―3―1 ワーキングメモリ容量による文理解の個人差
8―3―2 統語的複雑さの処理
8―3―3 言語的曖昧文の処理
8―3―4 語用論的処理と統語的処理の相互過程
8―4 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第9章 言語とジェスチャー
9―1 ジェスチャー研究の歴史
9―2 ジェスチャーの分類
9―3 表象的ジェスチャーの産出要因
9―3―1 聞き手要因
9―3―2 話し手要因
9―3―3 課題内容
9―4 こころ,ことば,表象的ジェスチャー
9―5 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
第10章 失語症
10―1 失語症研究の流れ
10―1―1 神経心理学の誕生
10―1―2 古典論の成立
10―1―3 全体論の台頭
10―2 失語症のタイプと症状
10―3 失語症患者における文発話の障害
10―3―1 語彙範疇の障害 新造語ジャーゴン
10―3―2 日本語話者における語彙範疇の障害
10―3―3 日本語話者における機能範疇の障害
10―3―4 文の生成プロセス
10―4 脳イメージング研究と失語症
10―5 まとめと今後の展望
【さらに読み進めたい人へ】
文 献
人名索引
事項索引
編者・執筆者紹介
装幀=虎尾 隆