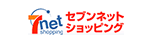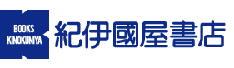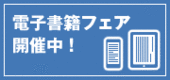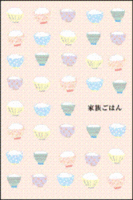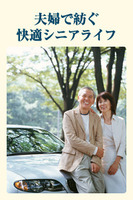相互行為の人類学
「心」と「文化」が出会う場所

| 著者 | 高田 明 著 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 教養・読みもの |
| 出版年月日 | 2019/02/01 |
| ISBN | 9784788516076 |
| 判型・ページ数 | A5・248ページ |
| 定価 | 本体2,800円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
日常的な相互行為における「意味のやりとり」を丹念に分析することで,心理学,人類学いずれとも異なる視点から「心」と「文化」をとらえなおし,二つの分野を架橋する「相互行為の人類学」。具体的な研究例をとおして,その手法と魅力を伝える入門書。
相互行為の人類学 目次
はしがき
第1章 相互行為の人類学への招待
第 1節 はじめに
第 2節 人類学と心理学の関わり
第 3節 内容の概要
第 4節 本書の成り立ちについて
第2章 理論と方法
第 1節 人類学における 4つのアプローチ
第 2節 文化人類学・言語人類学の特徴
1 社会・文化の研究を行う
2 フィールドワークを通じた参与観察を主たる研究手法とする
3 実践者の視点から社会・文化を理解することを目指す
第 3節 相互行為の人類学の射程と手法
1 特徴づけを正当化する 2つの解決策
2 相互行為の人類学で用いられる記号
3 基本的な分析概念
第 4節 まとめ
■第 2章についてのQ&A
第3章 社会的認知
第 1節 民俗分類
1 分類は文化である
2 東アフリカの牧畜民ボディの色・模様分類
第 2節 在来知への相互行為論的アプローチ
1 在来知をめぐる諸問題
2 グイ/ガナの生活様式
3 グイ/ガナの道探索実践
4 ブッシュで道を見つける
第 3節 まとめ
■第 3章についてのQ&A
第4章 他者理解
第 1節 人類学者の懊悩:他者の理解は可能か?
第 2節 懐疑主義を超えて
1 カラハリ論争と先住民運動
2 大型類人猿と基本的人権
3 根本的経験論と相互行為論的アプローチ
第 3節 グイ/ガナの道案内における相互理解の達成
1 ランドマークとしての樹木
2 スタンス,同意,相互理解
第 4節 人 ―チンパンジー間相互行為における相互理解の構成
1 チンパンジーの認知的能力,コミュニケーションの特徴
2 飼育下における人 ―チンパンジー間相互行為
3 チンパンジーの社会再考
第 5節 まとめ
■第 4章についてのQ&A
第5章 発達と社会化
第 1節 養育者 ―乳児間相互行為における社会システムの形成
1 リズムと調節の共有(誕生~)
2 注意の共有( 2カ月ごろ~)
3 記憶の共有( 8カ月ごろ~)
4 シンボルの共有(14カ月ごろ~)
第 2節 社会化に対する相互行為の人類学的アプローチ
1 行動の相互調整における文化的基盤
2 養育の複合的文脈
3 養育活動におけるリズムの共同的な創造
4 共同的音楽性と発話共同体
5 養育者 ―子ども間相互行為における「文化」再考
第 3節 誕生前の言語的社会化
1 妊娠をめぐる家族コミュニケーション
2 家族コミュニケーションの資源としての妊婦の身体感覚
3 妊娠期における家族関係の再編
第 4節 まとめ
■第 5章についてのQ&A
第6章 言語とコミュニケーション
第 1節 文化相対主義の隆盛
第 2節 相互行為の人類学における言語とコミュニケーション
第 3節 米国における依存性ジレンマ(Ochs & Izquierdo 2009)
第 4節 「思いやり」の実践
1 養育者による行為指示:直接 ―間接性の次元
2 養育者の行為指示に対する子どもの応答
3 日本の養育者 ―子ども間相互行為における文化的な特徴の再検討
第 5節 まとめ
■第 6章についてのQ&A
第7章 感情
第 1節 小説における感情
第 2節 感情研究における 4つのアプローチ
第 3節 間主観性(intersubjectivity)の基盤としての感情
1 初期音声コミュニケーションの研究
2 初期音声コミュニケーションにおける音楽性
3 サオ・カム(“あやす方法”)
4 IDSの詩化
5 初期音声コミュニケーションと感情
第 4節 会話に用いられる感情語彙
1 東アジアにおける「恥」の文化
2 日本語のCCIにおける「恥ずかしい」
3 「恥」の文化論再考
第 5節 まとめ
■第 7章についてのQ&A
第8章 結論にかえて
第 1節 各章のまとめ
第 2節 心的カテゴリーの脱構築
第 3節 文化的実践,慣習,社会制度
第 4節 フィールドワークの魅惑
第 5節 おわりに
引用文献
人名索引
事項索引
装幀=新曜社デザイン室
装画=高田 明
はしがき
第1章 相互行為の人類学への招待
第 1節 はじめに
第 2節 人類学と心理学の関わり
第 3節 内容の概要
第 4節 本書の成り立ちについて
第2章 理論と方法
第 1節 人類学における 4つのアプローチ
第 2節 文化人類学・言語人類学の特徴
1 社会・文化の研究を行う
2 フィールドワークを通じた参与観察を主たる研究手法とする
3 実践者の視点から社会・文化を理解することを目指す
第 3節 相互行為の人類学の射程と手法
1 特徴づけを正当化する 2つの解決策
2 相互行為の人類学で用いられる記号
3 基本的な分析概念
第 4節 まとめ
■第 2章についてのQ&A
第3章 社会的認知
第 1節 民俗分類
1 分類は文化である
2 東アフリカの牧畜民ボディの色・模様分類
第 2節 在来知への相互行為論的アプローチ
1 在来知をめぐる諸問題
2 グイ/ガナの生活様式
3 グイ/ガナの道探索実践
4 ブッシュで道を見つける
第 3節 まとめ
■第 3章についてのQ&A
第4章 他者理解
第 1節 人類学者の懊悩:他者の理解は可能か?
第 2節 懐疑主義を超えて
1 カラハリ論争と先住民運動
2 大型類人猿と基本的人権
3 根本的経験論と相互行為論的アプローチ
第 3節 グイ/ガナの道案内における相互理解の達成
1 ランドマークとしての樹木
2 スタンス,同意,相互理解
第 4節 人 ―チンパンジー間相互行為における相互理解の構成
1 チンパンジーの認知的能力,コミュニケーションの特徴
2 飼育下における人 ―チンパンジー間相互行為
3 チンパンジーの社会再考
第 5節 まとめ
■第 4章についてのQ&A
第5章 発達と社会化
第 1節 養育者 ―乳児間相互行為における社会システムの形成
1 リズムと調節の共有(誕生~)
2 注意の共有( 2カ月ごろ~)
3 記憶の共有( 8カ月ごろ~)
4 シンボルの共有(14カ月ごろ~)
第 2節 社会化に対する相互行為の人類学的アプローチ
1 行動の相互調整における文化的基盤
2 養育の複合的文脈
3 養育活動におけるリズムの共同的な創造
4 共同的音楽性と発話共同体
5 養育者 ―子ども間相互行為における「文化」再考
第 3節 誕生前の言語的社会化
1 妊娠をめぐる家族コミュニケーション
2 家族コミュニケーションの資源としての妊婦の身体感覚
3 妊娠期における家族関係の再編
第 4節 まとめ
■第 5章についてのQ&A
第6章 言語とコミュニケーション
第 1節 文化相対主義の隆盛
第 2節 相互行為の人類学における言語とコミュニケーション
第 3節 米国における依存性ジレンマ(Ochs & Izquierdo 2009)
第 4節 「思いやり」の実践
1 養育者による行為指示:直接 ―間接性の次元
2 養育者の行為指示に対する子どもの応答
3 日本の養育者 ―子ども間相互行為における文化的な特徴の再検討
第 5節 まとめ
■第 6章についてのQ&A
第7章 感情
第 1節 小説における感情
第 2節 感情研究における 4つのアプローチ
第 3節 間主観性(intersubjectivity)の基盤としての感情
1 初期音声コミュニケーションの研究
2 初期音声コミュニケーションにおける音楽性
3 サオ・カム(“あやす方法”)
4 IDSの詩化
5 初期音声コミュニケーションと感情
第 4節 会話に用いられる感情語彙
1 東アジアにおける「恥」の文化
2 日本語のCCIにおける「恥ずかしい」
3 「恥」の文化論再考
第 5節 まとめ
■第 7章についてのQ&A
第8章 結論にかえて
第 1節 各章のまとめ
第 2節 心的カテゴリーの脱構築
第 3節 文化的実践,慣習,社会制度
第 4節 フィールドワークの魅惑
第 5節 おわりに
引用文献
人名索引
事項索引
装幀=新曜社デザイン室
装画=高田 明