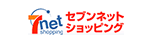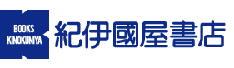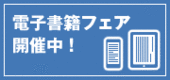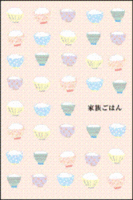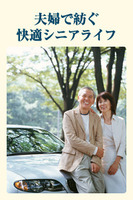近刊
文化とは何か,どこにあるのか
対立と共生をめぐる心理学

| 著者 | 山本 登志哉 著 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 教養・読みもの |
| 出版年月日 | 2015/10/05 |
| ISBN | 9784788514478 |
| 判型・ページ数 | 4-6・216ページ |
| 定価 | 本体2,400円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
目に見えず,触れることもできない文化。その主体は個人か集団か? 精神的なものか物質的なものか? なぜ文化は変化するのか? ひとびとが対立し,助け合い,憎しみ合い,愛し合いながら共に生きる,「私の体験」から立ち上がる新しい心理学の誕生。
文化とは何か、どこにあるのか ――目次
はじめに
序章 文化とは何か
0―1 文化―対立と共生を生むもの
0―2 心―普遍から具体へ
0―3 文化って何?
0―4 つながり方としての文化―生活者の「見え」から考える
第?部 文化の立ち現われ方
第1章 文化はどう現われる
1―1 文化の主観性
1―2 文化の客観性
1―3 まとめ―主観的客観の世界
第2章 文化が現われる文脈
2―1 意図と文化
2―2 文化一歩前
2―3 表現と規範
2―4 文化と集団
【エピソード1】気をもらう
2―5 まとめ―共同性の差という文脈に現れる文化
第3章 文化集団の虚構性
3―1 文化の担い手―個人か集団か
3―2 文化はどこに?―空間的外延について
【エピソード2】値引き
3―3 いつからある?―時間的外延について
3―4 メンバーは誰?―成員的外延について
3―5 文化を分ける特徴は?―内包について
3―6 まとめ―ぼやける文化集団の境界線
第4章 文化集団の実体性
4―1 カルチャーショック
【エピソード3】奪い取られる
【コラム1】謝罪の文化論
4―2 線が壁になるとき
4―3 お金という虚構の力
4―4 社会的実践と機能的実体化
4―5 まとめ―規範的要素の機能的実体化
第5章 文化集団の立ち現われ
5―1 逸脱が文化差となる時
【エピソード4】性格か文化か
5―2 差の認識から生み出される文化集団
【コラム2】文化の実体化が多文化教育に持つ実践的な意味
5―3 原因帰属と関係調整法
5―4 まとめ―文化集団の認識と関係調整
【コラム3】星座の実体性
第?部 文化の語り方
第6章 拡張された媒介構造=EMS
6―1 対象を介した相互作用の構図
6―2 人間の社会的行動の一般構造
6―3 揺れ動くEMS
6―4 まとめ―人間社会を成り立たせるEMS
第7章 EMSと集団の実体化
7―1 「合意」として成り立つEMS
【エピソード5】おもちゃの奪い合い
【コラム4】「見る ⇔ 見られる」関係と集団の実体化
7―2 異質な規範的媒介項の抑圧的調整
7―3 主体の二重化と主体間の平等性
【エピソード6】主体の二重化
7―4 規範的媒介項の「主体」としての集団
7―5 まとめ―EMSを安定化させる集団の実体化
第8章 文化集団の実体化とEMS
8―1 集団間関係という人間的問題
8―2 EMSと水平的・垂直的組織
8―3 主体の二重化と階層的入れ子的集団構造
【コラム5】儒教的社会理論とEMS
8―4 規範的媒介項のズレと集団の実体化
【エピソード7】私の物とは?
8―5 まとめ―文化実践としての文化認識
第9章 文化意識の実践性と文化研究
9―1 比較文化研究が立ち上がるとき
【エピソード8】手のつなぎ方の文化性
9―2 眼差しの差としての文化差
【エピソード9】どうしておごらないの
9―3 文化が発生する次元としての規範性・共同性
9―4 主観的現象の客観的研究とは
9―5 文化の対話的客観化
9―6 対話実践としての文化研究と具体的一般化
9―7 本書のまとめ―文化とは何か
【コラム6】文化が個人に先立つものとして現われる理由
おわりに
注
文献
索引
カバー・本文中手描きイラスト=山本つむぎ
はじめに
序章 文化とは何か
0―1 文化―対立と共生を生むもの
0―2 心―普遍から具体へ
0―3 文化って何?
0―4 つながり方としての文化―生活者の「見え」から考える
第?部 文化の立ち現われ方
第1章 文化はどう現われる
1―1 文化の主観性
1―2 文化の客観性
1―3 まとめ―主観的客観の世界
第2章 文化が現われる文脈
2―1 意図と文化
2―2 文化一歩前
2―3 表現と規範
2―4 文化と集団
【エピソード1】気をもらう
2―5 まとめ―共同性の差という文脈に現れる文化
第3章 文化集団の虚構性
3―1 文化の担い手―個人か集団か
3―2 文化はどこに?―空間的外延について
【エピソード2】値引き
3―3 いつからある?―時間的外延について
3―4 メンバーは誰?―成員的外延について
3―5 文化を分ける特徴は?―内包について
3―6 まとめ―ぼやける文化集団の境界線
第4章 文化集団の実体性
4―1 カルチャーショック
【エピソード3】奪い取られる
【コラム1】謝罪の文化論
4―2 線が壁になるとき
4―3 お金という虚構の力
4―4 社会的実践と機能的実体化
4―5 まとめ―規範的要素の機能的実体化
第5章 文化集団の立ち現われ
5―1 逸脱が文化差となる時
【エピソード4】性格か文化か
5―2 差の認識から生み出される文化集団
【コラム2】文化の実体化が多文化教育に持つ実践的な意味
5―3 原因帰属と関係調整法
5―4 まとめ―文化集団の認識と関係調整
【コラム3】星座の実体性
第?部 文化の語り方
第6章 拡張された媒介構造=EMS
6―1 対象を介した相互作用の構図
6―2 人間の社会的行動の一般構造
6―3 揺れ動くEMS
6―4 まとめ―人間社会を成り立たせるEMS
第7章 EMSと集団の実体化
7―1 「合意」として成り立つEMS
【エピソード5】おもちゃの奪い合い
【コラム4】「見る ⇔ 見られる」関係と集団の実体化
7―2 異質な規範的媒介項の抑圧的調整
7―3 主体の二重化と主体間の平等性
【エピソード6】主体の二重化
7―4 規範的媒介項の「主体」としての集団
7―5 まとめ―EMSを安定化させる集団の実体化
第8章 文化集団の実体化とEMS
8―1 集団間関係という人間的問題
8―2 EMSと水平的・垂直的組織
8―3 主体の二重化と階層的入れ子的集団構造
【コラム5】儒教的社会理論とEMS
8―4 規範的媒介項のズレと集団の実体化
【エピソード7】私の物とは?
8―5 まとめ―文化実践としての文化認識
第9章 文化意識の実践性と文化研究
9―1 比較文化研究が立ち上がるとき
【エピソード8】手のつなぎ方の文化性
9―2 眼差しの差としての文化差
【エピソード9】どうしておごらないの
9―3 文化が発生する次元としての規範性・共同性
9―4 主観的現象の客観的研究とは
9―5 文化の対話的客観化
9―6 対話実践としての文化研究と具体的一般化
9―7 本書のまとめ―文化とは何か
【コラム6】文化が個人に先立つものとして現われる理由
おわりに
注
文献
索引
カバー・本文中手描きイラスト=山本つむぎ