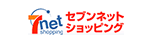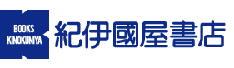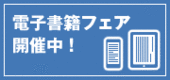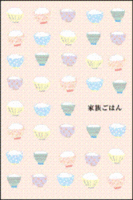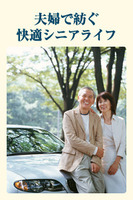フーコー 思想の考古学
思考しえないものを思考するフーコーの「考古学」は,どのように創出されたか。『狂気の歴史』『臨床医学の誕生』『言葉と物』などを丁寧に読み解いて,「狂気へのまなざし」から考古学,系譜学への道筋を明らかにし,カント「人間学」批判にいたる。
◆フーコー 思想の考古学――目次
第一章 フーコーの初期―『精神疾患とパーソナリティ』
第一節 精神医学の問題点
フーコーの処女作の意味 フーコーの最初の問題 心理学の擬似―科学性
第二節 精神の疾患の主観性の分析
意識の地層モデル―発達論とその難点 意識の歴史性のモデル―不安の発生 意識の実存論的なモデル
第三節 実存分析と人間学
現存在分析の意味 夢の体験と実存 現存在分析の限界 夢の価値狂気の逆説
第四節 疾患の客観性の分析
狂気の社会的な意味 パブロフ理論 ソ連と精神医学
第二章 狂気の経験―『狂気の歴史』
第一節 狂気の歴史の可能性
二つの歴史 狂気の歴史の可能性 精神医学という学問への疑念
第二節 狂気の批判性と悲劇性 56
中世における非理性 非理性の三つの形象―愚者、道化、怪物 狂気の悲劇性 狂気の批判的な性格 悲劇的なものの衝撃
第三節 古典主義の時代の狂気
デカルトにおける切断 大いなる閉じ込め 狂気と道徳
第四節 狂気の新しい分類
医学と道徳の「同じ夢」 狂気についての新しい感受性 新しい自然狂気の分割 狂者の「解放」
第五節 心理学の誕生
狂気と法の新しい関係 理性の他者 ヘーゲルの人間学 心理学という学問の限界
第三章 狂気と文学―『レイモン・ルーセル』
第一節 作品の不在
作品の可能性 言語の力
第二節 ルーセルにおける三つの逆説
ルーセルの魅力 三つの逆説 「わたしは嘘をついている」 ルーセルの手法 黒い太陽 「わたしは死んでいる」 「わたしは狂っている」 三つの逆説の意味
第三節 アルトーにおける三つの逆説
「わたしは狂っている」 「わたしは死んでいる」 アルトーの苦闘 演劇と身体 「わたしは嘘をついている」 カバン語と残酷の演劇 舌語 晩年のアルトー
第四章 死と科学―『臨床医学の誕生』
第一節 医学のまなざしの意味
『レイモン・ルーセル』と『臨床医学の誕生』の隠れた結びつき 科学としての医学の誕生 三つの時代区分
第二節 近代的な医学の誕生
都市の統治 近代的な臨床医学の登場 解剖学的なまなざし 死の特権的な地位 医学的まなざしの転換 見えるものと見えないもの
第五章 考古学の方法―『知の考古学』
第一節 考古学とは
考古学のねらい 道具の考古学
第二節 『知の考古学』
考古学の方法論的な解明 考古学とエピステモロジー 不連続性の概念 対象領域の拡大 ディスクール エノンセの定義 エノンセの機能 エノンセとディスクールの関係 歴史的なアプリオリ 真理のうちにあること 知 三つの領域における知―生物学、経済学、言語学 知への意志と真理への意志 アルシーヴ 作者の死 同時代の診断
第六章 思想の考古学―『言葉と物』
第一節 『言葉と物』の方法
物と秩序 中間の領域 エピステーメーの切断
第二節 エピステーメーの秩序
「世界の散文」 ベーコンとデカルト タブローの空間 古典主義時代の知の方法論 古典主義時代における三つの基本的な学問 欲望の時代 考古学と現代の診断
第三節 近代のエピステーメーの登場
経済学の誕生 生物学の誕生 文献学の誕生
第四節 〈人間〉の誕生
人間の有限性と知 近代の知の特徴
第七章 人間学の「罠」と現代哲学の課題―「カント『人間学』の序」
第一節 カントの人間学
カントの人間学の位置 起源としてのカントの哲学 現代哲学の諸潮流
第二節 カント批判の論拠
『人間学』と批判前期 『人間学』と批判期 『人間学』と批判後期 家族の人間学―第二の問題系 嫉妬の人間学 理性の逸脱―第三の問題系 『人間学』と『批判』書の関係 『人間学』における問題の深化 カントの『遺稿』の位置 世界の三重の構造
第三節 カントと現代哲学
現代哲学への批判 神、世界、人間 アプリオリの概念の逆転 人間学の罠
第四節 人間学の四辺形
哲学の可能性 二組の線分 存在論と動詞の理論 言語の起源と指示 アルファベットと派生の理論 近代のエピステーメー 人間学の四辺形の成立
第五節 人間の有限性
有限性の分析論 経験的=超越論的な二重性 二つのまなざし コギトと考えられぬもの ?盲目的なしみ〉と哲学 起源への回帰 起源に回帰する二つの道 人間学の四辺形を超えて
注
あとがき
索引
装幀―桂川潤
装画―BUshi
第一章 フーコーの初期―『精神疾患とパーソナリティ』
第一節 精神医学の問題点
フーコーの処女作の意味 フーコーの最初の問題 心理学の擬似―科学性
第二節 精神の疾患の主観性の分析
意識の地層モデル―発達論とその難点 意識の歴史性のモデル―不安の発生 意識の実存論的なモデル
第三節 実存分析と人間学
現存在分析の意味 夢の体験と実存 現存在分析の限界 夢の価値狂気の逆説
第四節 疾患の客観性の分析
狂気の社会的な意味 パブロフ理論 ソ連と精神医学
第二章 狂気の経験―『狂気の歴史』
第一節 狂気の歴史の可能性
二つの歴史 狂気の歴史の可能性 精神医学という学問への疑念
第二節 狂気の批判性と悲劇性 56
中世における非理性 非理性の三つの形象―愚者、道化、怪物 狂気の悲劇性 狂気の批判的な性格 悲劇的なものの衝撃
第三節 古典主義の時代の狂気
デカルトにおける切断 大いなる閉じ込め 狂気と道徳
第四節 狂気の新しい分類
医学と道徳の「同じ夢」 狂気についての新しい感受性 新しい自然狂気の分割 狂者の「解放」
第五節 心理学の誕生
狂気と法の新しい関係 理性の他者 ヘーゲルの人間学 心理学という学問の限界
第三章 狂気と文学―『レイモン・ルーセル』
第一節 作品の不在
作品の可能性 言語の力
第二節 ルーセルにおける三つの逆説
ルーセルの魅力 三つの逆説 「わたしは嘘をついている」 ルーセルの手法 黒い太陽 「わたしは死んでいる」 「わたしは狂っている」 三つの逆説の意味
第三節 アルトーにおける三つの逆説
「わたしは狂っている」 「わたしは死んでいる」 アルトーの苦闘 演劇と身体 「わたしは嘘をついている」 カバン語と残酷の演劇 舌語 晩年のアルトー
第四章 死と科学―『臨床医学の誕生』
第一節 医学のまなざしの意味
『レイモン・ルーセル』と『臨床医学の誕生』の隠れた結びつき 科学としての医学の誕生 三つの時代区分
第二節 近代的な医学の誕生
都市の統治 近代的な臨床医学の登場 解剖学的なまなざし 死の特権的な地位 医学的まなざしの転換 見えるものと見えないもの
第五章 考古学の方法―『知の考古学』
第一節 考古学とは
考古学のねらい 道具の考古学
第二節 『知の考古学』
考古学の方法論的な解明 考古学とエピステモロジー 不連続性の概念 対象領域の拡大 ディスクール エノンセの定義 エノンセの機能 エノンセとディスクールの関係 歴史的なアプリオリ 真理のうちにあること 知 三つの領域における知―生物学、経済学、言語学 知への意志と真理への意志 アルシーヴ 作者の死 同時代の診断
第六章 思想の考古学―『言葉と物』
第一節 『言葉と物』の方法
物と秩序 中間の領域 エピステーメーの切断
第二節 エピステーメーの秩序
「世界の散文」 ベーコンとデカルト タブローの空間 古典主義時代の知の方法論 古典主義時代における三つの基本的な学問 欲望の時代 考古学と現代の診断
第三節 近代のエピステーメーの登場
経済学の誕生 生物学の誕生 文献学の誕生
第四節 〈人間〉の誕生
人間の有限性と知 近代の知の特徴
第七章 人間学の「罠」と現代哲学の課題―「カント『人間学』の序」
第一節 カントの人間学
カントの人間学の位置 起源としてのカントの哲学 現代哲学の諸潮流
第二節 カント批判の論拠
『人間学』と批判前期 『人間学』と批判期 『人間学』と批判後期 家族の人間学―第二の問題系 嫉妬の人間学 理性の逸脱―第三の問題系 『人間学』と『批判』書の関係 『人間学』における問題の深化 カントの『遺稿』の位置 世界の三重の構造
第三節 カントと現代哲学
現代哲学への批判 神、世界、人間 アプリオリの概念の逆転 人間学の罠
第四節 人間学の四辺形
哲学の可能性 二組の線分 存在論と動詞の理論 言語の起源と指示 アルファベットと派生の理論 近代のエピステーメー 人間学の四辺形の成立
第五節 人間の有限性
有限性の分析論 経験的=超越論的な二重性 二つのまなざし コギトと考えられぬもの ?盲目的なしみ〉と哲学 起源への回帰 起源に回帰する二つの道 人間学の四辺形を超えて
注
あとがき
索引
装幀―桂川潤
装画―BUshi