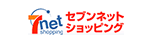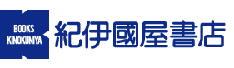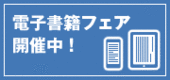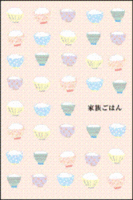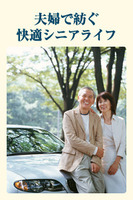社会調査史のリテラシー
方法を読む社会学的想像力
社会調査とは何か。社会調査史とは何か。その意義を観察や記述や分析の具体的な技法からたどり,「量的/質的」などの不毛な二分法的カテゴリーを根源から問い直す。「社会」と「社会学」についての思考を一新させる,研究者必読の刺激的論考集成。
社会調査史のリテラシー――目次
まえがき
1 日本近代における都市社会学の形成
一 日本都市社会学の歴史意識
二 可視化の実践とテクスト――方法史的分析の模索
三 累積する起源の変革力――まとめに代えて
2 モノグラフィの都市認識
3 東京市社会局調査を発掘する
一 調査研究のねらい
二 東京市社会局の誕生
三 基礎資料として集成する方法について
四 調査資料集成の基本方針
五 調査の視角――下層の可視化
六 今後の課題
4 コミュニティ調査の方法的課題
一 方法的課題とは何か
二 コミュニティ研究の視座構造――方法意識のあらわれとして
三 コミュニティ調査実践の三つの蓄積
四 方法論的多様性の構築にむけて――表層のテクスト化
5 ライフヒストリー研究の位相
一 『口述の生活史』の問題提起
二 フィールドとしての個人
三 口述の方法性
6 量的方法と質的方法が対立する地平
方法論議の意味 二項対立の大文字化 二項対立の歴史性 チェーピンの分類 二項性の浮上と集約 岩波全書版『社会調査』 相互補完による自己完結 非対称性と時代性 社会調査の流行 対立の地平の展開形態 データ批判と形式分析
7 コミュニケーションとしての調査
一 耳の採集――ことばで知るということ
二 聞き書きというドラマ――取り調べ・尋問から生活史まで
三 方法としての調査票――複合的な方法性の構築にむけて
8 内容分析とメディア形式の分析
「身の上相談」分析の新しさ メディア空間の変容 手法と素材を問われる
9 調査史のなかの『都市の日本人』
方法と場とを読む 日本における社会調査の展開 方法意識をしばる対立 豊かな折衷主義 調査票(質問紙)のもつ意味 調査票以前あるいは調査票以外 調査をある密度にまで押し上げる 質問するという社会行為 資料の多面性をふまえつつ 後発効果論を生かせる枠組みの必要
10 調査のなかの権力を考える
一 関係性の解読と共生
二 調査のなかの権力をめぐって
三 観察と対話の位相
11 厚みのある記述をつくる
一 モノグラフとは何か――「グラフgraph」の意味
二 分厚さの構築――記述のなかの分析
三 経験に学ぶ――モノグラフへの参与
四 謎解きの物語――探偵小説というモデル
12 国勢調査「美談逸話」考
一 『日本国勢調査記念録』と第一回国勢調査
二 調査への動員――名誉と献身の物語
三 奇談への逸脱――権力と主体性
13 社会調査データベースと書誌学的想像力
文化財としての調査資料 印刷物としての質問紙 四つの要素の複合体として 作品としての調査票とライブラリー 社会調査史の不在 社会調査論と認識の生産 エフェメラの書誌学 『都市の日本人』 「L.S.」と「K.S.」 質問紙以外 データの多次元性と読者の批判力 ぶ厚い共有に向けて 非文字資料の資源化 画像資料批判
14 テクノロジーと記録の社会性
一 テクストをめぐるテクノロジー
二 方法史の領域と調査実践の分析
三 社会地図と空間記述
四 集計を立ちあげる記述
五 生活を書きとめる
六 テクストとしての写真
七 テクノロジーとしてのリテラシー
15 図を考える/図で考える
一 学問の名前
二 絵引の発想と画像データベース
三 「網のようなもの」を編む
16 『社会調査ハンドブック』の方法史的解読
一 素材としての技法書
二 『社会調査ハンドブック』の内容分析
三 結論――ハンドブック構想の原点
17 「質的データ」論 再考
疑似問題とニセの解答 「方法論的基礎づけ」を立ち上げる 「一つ」への統合をめぐって 複雑な分割線の重なりあい 社会調査論の四つの意味 「理論と調査」もしくは「理論と実践」という分割線 調査という実践の場 方法の論理学 「すれ違い」を見落とさない 「質的データ」としての実体化 データの質 社会学史と社会調査史 テクストとしての社会
18 社会調査のイデオロギーとテクノロジー
一 「社会調査論」の再検討
二 質問紙のテクノロジーと「統計的研究法」の構成
三 「社会調査への信頼形成」問題――シンポジウム組織者の問いに
19 地域社会に対するリテラシー
一 方法史的認識を戦略として立ち上げる
二 地域社会調査史の構造を鳥瞰する
三 地域社会学と「郷土研究」――構造を内側から認識する主体
20 都市を解読する力の構築
一 都市カテゴリーの位相とエスノグラフィの実践
二 都市の不可視性――壁と構造と歴史と
三 フィールドノートを書く/エスノグラフィを編む
あとがき
文献一覧
索引
装幀=
まえがき
1 日本近代における都市社会学の形成
一 日本都市社会学の歴史意識
二 可視化の実践とテクスト――方法史的分析の模索
三 累積する起源の変革力――まとめに代えて
2 モノグラフィの都市認識
3 東京市社会局調査を発掘する
一 調査研究のねらい
二 東京市社会局の誕生
三 基礎資料として集成する方法について
四 調査資料集成の基本方針
五 調査の視角――下層の可視化
六 今後の課題
4 コミュニティ調査の方法的課題
一 方法的課題とは何か
二 コミュニティ研究の視座構造――方法意識のあらわれとして
三 コミュニティ調査実践の三つの蓄積
四 方法論的多様性の構築にむけて――表層のテクスト化
5 ライフヒストリー研究の位相
一 『口述の生活史』の問題提起
二 フィールドとしての個人
三 口述の方法性
6 量的方法と質的方法が対立する地平
方法論議の意味 二項対立の大文字化 二項対立の歴史性 チェーピンの分類 二項性の浮上と集約 岩波全書版『社会調査』 相互補完による自己完結 非対称性と時代性 社会調査の流行 対立の地平の展開形態 データ批判と形式分析
7 コミュニケーションとしての調査
一 耳の採集――ことばで知るということ
二 聞き書きというドラマ――取り調べ・尋問から生活史まで
三 方法としての調査票――複合的な方法性の構築にむけて
8 内容分析とメディア形式の分析
「身の上相談」分析の新しさ メディア空間の変容 手法と素材を問われる
9 調査史のなかの『都市の日本人』
方法と場とを読む 日本における社会調査の展開 方法意識をしばる対立 豊かな折衷主義 調査票(質問紙)のもつ意味 調査票以前あるいは調査票以外 調査をある密度にまで押し上げる 質問するという社会行為 資料の多面性をふまえつつ 後発効果論を生かせる枠組みの必要
10 調査のなかの権力を考える
一 関係性の解読と共生
二 調査のなかの権力をめぐって
三 観察と対話の位相
11 厚みのある記述をつくる
一 モノグラフとは何か――「グラフgraph」の意味
二 分厚さの構築――記述のなかの分析
三 経験に学ぶ――モノグラフへの参与
四 謎解きの物語――探偵小説というモデル
12 国勢調査「美談逸話」考
一 『日本国勢調査記念録』と第一回国勢調査
二 調査への動員――名誉と献身の物語
三 奇談への逸脱――権力と主体性
13 社会調査データベースと書誌学的想像力
文化財としての調査資料 印刷物としての質問紙 四つの要素の複合体として 作品としての調査票とライブラリー 社会調査史の不在 社会調査論と認識の生産 エフェメラの書誌学 『都市の日本人』 「L.S.」と「K.S.」 質問紙以外 データの多次元性と読者の批判力 ぶ厚い共有に向けて 非文字資料の資源化 画像資料批判
14 テクノロジーと記録の社会性
一 テクストをめぐるテクノロジー
二 方法史の領域と調査実践の分析
三 社会地図と空間記述
四 集計を立ちあげる記述
五 生活を書きとめる
六 テクストとしての写真
七 テクノロジーとしてのリテラシー
15 図を考える/図で考える
一 学問の名前
二 絵引の発想と画像データベース
三 「網のようなもの」を編む
16 『社会調査ハンドブック』の方法史的解読
一 素材としての技法書
二 『社会調査ハンドブック』の内容分析
三 結論――ハンドブック構想の原点
17 「質的データ」論 再考
疑似問題とニセの解答 「方法論的基礎づけ」を立ち上げる 「一つ」への統合をめぐって 複雑な分割線の重なりあい 社会調査論の四つの意味 「理論と調査」もしくは「理論と実践」という分割線 調査という実践の場 方法の論理学 「すれ違い」を見落とさない 「質的データ」としての実体化 データの質 社会学史と社会調査史 テクストとしての社会
18 社会調査のイデオロギーとテクノロジー
一 「社会調査論」の再検討
二 質問紙のテクノロジーと「統計的研究法」の構成
三 「社会調査への信頼形成」問題――シンポジウム組織者の問いに
19 地域社会に対するリテラシー
一 方法史的認識を戦略として立ち上げる
二 地域社会調査史の構造を鳥瞰する
三 地域社会学と「郷土研究」――構造を内側から認識する主体
20 都市を解読する力の構築
一 都市カテゴリーの位相とエスノグラフィの実践
二 都市の不可視性――壁と構造と歴史と
三 フィールドノートを書く/エスノグラフィを編む
あとがき
文献一覧
索引
装幀=