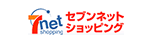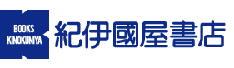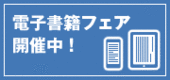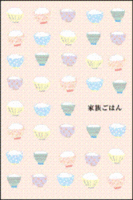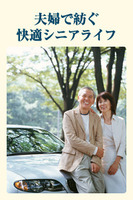不協和音の宇宙へ
モンテスキューの社会学
「理性」「進歩」を主導概念とした啓蒙主義の時代に,モンテスキューは多様性と不協和音こそが自由の証だと主張し,社会学の始原となった。『ペルシャ人の手紙』などを丁寧に辿りながら,同質化し不寛容になっていく現代の閉塞状況に新風を吹込む力作。
不協和音の宇宙へ――目次
はじめに
凡例
第一部 抵抗と呪縛―普遍概念をめぐる格闘
第一章 ボシュエ―あるいは近代への精神的転回について
1 地上における神の国―王と教皇の狭間で
2 幸福なる国家の条件をめぐって―アウグスティヌスとボシュエ
3 歴史が無用となるとき―ボシュエの歴史観
4 真理と幸福の亀裂―ボシュエがリベルタンに見たもの
5 近代―それは新しい展開か、あるいは新しい仮面か
第二章 揺るがす力と揺らぐ挑戦―啓蒙主義
1 寛容と絶対の相克―ヴォルテール
2 神なき普遍の探求―ディドロ
第三章 忘れられた幸福―コントの実証主義と社会学
1 「実証」の意義
2 歴史法則としての実証的精神
3 社会有機体と自由検討
4 幸福と実証的精神の矛盾
第四章 法と法則の二元論へのとまどい―モンテスキューとデュルケム
1 デュルケムの出発点への問いかけ
2 モンテスキューからデュルケムへ―その継承と断絶
3 法則のイデオロギー化/法の透明化
4 当為の呪縛と社会学の自由
5 デュルケムの根本問題
第二部 多様性と相互性──モンテスキューの相対主義
第一章 社会は分裂していなければならない
1 分裂し、かつ多様な社会をあつかうこと
2 分裂は社会的繁栄の条件である
3 境界と相互性の消失―腐敗が意味するもの
4 不協和音に満ちていない平和などない
第二章 不合理ではない、しかし理解不可能―自然法
1 習俗―楽園の喪失をめぐって
2 自然へのまなざし―科学的精神への希望
3 自然法則の明証性と道徳の根拠
4 不完全な人々よ、求めよ。されど与えられぬ
5 自然法と適合的関係―神もまたみずからを制限する
第三章 愛と矛盾―有機体はうごめく
1 自然は人にすべてを与えている―幸福と自己愛の所在
2 幸福と社会―パラドックスの物語
3 情念の反-秩序
4 子供が生まれる―人口動態のあらわすもの
5 「趣向」の誕生―自然は修復する
第四章 自由の多層性と社会の力学
1 エスプリは世界を跳ねまわる
2 自由とは不完全さのことである
3 豊かさが富によって荒廃するとき
4 四つの自由と市民精神
5 多様性の連結体としての世界―社会は必要だ、しかし国家は?
結 び
1 変化しつづける多様な社会をいかに記述するか
2 異質な世界を見わたす思考
3 文学と社会学―つながりのありか
4 相対主義の陥穽を超えて―多元主義の社会学へ
註
あとがき
索引
装幀―難波園子
はじめに
凡例
第一部 抵抗と呪縛―普遍概念をめぐる格闘
第一章 ボシュエ―あるいは近代への精神的転回について
1 地上における神の国―王と教皇の狭間で
2 幸福なる国家の条件をめぐって―アウグスティヌスとボシュエ
3 歴史が無用となるとき―ボシュエの歴史観
4 真理と幸福の亀裂―ボシュエがリベルタンに見たもの
5 近代―それは新しい展開か、あるいは新しい仮面か
第二章 揺るがす力と揺らぐ挑戦―啓蒙主義
1 寛容と絶対の相克―ヴォルテール
2 神なき普遍の探求―ディドロ
第三章 忘れられた幸福―コントの実証主義と社会学
1 「実証」の意義
2 歴史法則としての実証的精神
3 社会有機体と自由検討
4 幸福と実証的精神の矛盾
第四章 法と法則の二元論へのとまどい―モンテスキューとデュルケム
1 デュルケムの出発点への問いかけ
2 モンテスキューからデュルケムへ―その継承と断絶
3 法則のイデオロギー化/法の透明化
4 当為の呪縛と社会学の自由
5 デュルケムの根本問題
第二部 多様性と相互性──モンテスキューの相対主義
第一章 社会は分裂していなければならない
1 分裂し、かつ多様な社会をあつかうこと
2 分裂は社会的繁栄の条件である
3 境界と相互性の消失―腐敗が意味するもの
4 不協和音に満ちていない平和などない
第二章 不合理ではない、しかし理解不可能―自然法
1 習俗―楽園の喪失をめぐって
2 自然へのまなざし―科学的精神への希望
3 自然法則の明証性と道徳の根拠
4 不完全な人々よ、求めよ。されど与えられぬ
5 自然法と適合的関係―神もまたみずからを制限する
第三章 愛と矛盾―有機体はうごめく
1 自然は人にすべてを与えている―幸福と自己愛の所在
2 幸福と社会―パラドックスの物語
3 情念の反-秩序
4 子供が生まれる―人口動態のあらわすもの
5 「趣向」の誕生―自然は修復する
第四章 自由の多層性と社会の力学
1 エスプリは世界を跳ねまわる
2 自由とは不完全さのことである
3 豊かさが富によって荒廃するとき
4 四つの自由と市民精神
5 多様性の連結体としての世界―社会は必要だ、しかし国家は?
結 び
1 変化しつづける多様な社会をいかに記述するか
2 異質な世界を見わたす思考
3 文学と社会学―つながりのありか
4 相対主義の陥穽を超えて―多元主義の社会学へ
註
あとがき
索引
装幀―難波園子