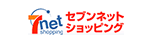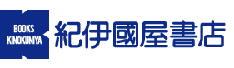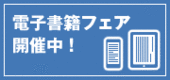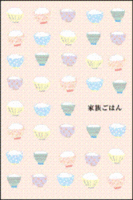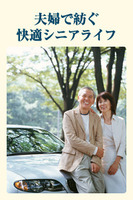発達をうながす教育心理学
大人はどうかかわったらいいのか

| 著者 | 山岸 明子 著 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 発達・教育 |
| 出版年月日 | 2009/06/20 |
| ISBN | 9784788511675 |
| 判型・ページ数 | A5・224ページ |
| 定価 | 本体2,200円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
子どもの発達を促すために,大人はどう働きかけるべきか。社会的事件や小説・映画を事例にし,理論的・実証的な研究に基づく学習と生きた理解とが,相乗的に深められるテキスト。教職を目指す人や,人間の発達にかかわる人・援助者にも役立つ一冊。
目次
はじめに
教育心理学とはどういう学問か、なぜ学ぶ必要があるのか
本書の概要
第I部 発達と教育
第1章 教育がもつ2つの側面と、現在の教育状況
1 教育がもつ2つの側面
2 2つの大人のかかわり方と教育状況の変遷
3 現代社会と主体的・能動的学び
第2章 発達における経験の重要性と発達の可塑性
1 発達における遺伝と環境
2 初期経験の重要性
3 人間の発達の特殊性
4 発達の可塑性 ― 初期経験の効果の持続性
第II部 発達・学習のとらえ方と学習の方法
第3章 大人主導の発達・学習・教育観 ― 行動主義の学習・教育観
1 学習成立の理論 ― 条件づけ
2 教育への応用(1)― プログラム学習
3 教育への応用(2)― 行動療法
第4章 子どもの能動性を重視する発達・学習・教育観
― ピアジェの発達・教育観
1 ピアジェの認知発達理論
2 ピアジェ理論から導かれる大人・教育の役割
3 子どもの能動性を重視する学習法
4 行動主義的考え方とピアジェ的考え方の比較、
および併用の必要性
第5章 子どもの能動性を考慮しつつ大人の働きかけを重視する発達・
学習・教育観 ― 認知心理学の立場
1 知識の構成化の理論
2 状況主義・状況的認知理論
第III部 道徳性・社会性の発達と教育
第6章 大人主導の道徳性発達の考え方
1 精神分析理論
2 社会的学習理論
3 日本の道徳教育への示唆
第7章 道徳性の認知発達理論 ― 子どもの能動性を重視する立場
1 ピアジェの道徳性発達の理論
2 コールバーグ理論
3 コールバーグ以後の理論と日本の教育への示唆
第8章 道徳性・社会性の発達における大人の役割 ― 望ましくない行動
への対処
第IV部 自己学習を可能にするもの
第9章 内発的動機づけ
1 内発的動機づけ
2 内発的動機づけに基づく学習
第10章 自己効力感、有能感
1 自己効力感、有能感
2 原因帰属
3 無力感の獲得
4 現代青少年の無気力の原因
5 無力感の克服
第11章 メタ認知
1 自己制御学習
2 メタ認知
3 メタ認知の育成
おわりに
文献
索引
コラム
1-1 自主性の尊重と集団との軋轢
1-2 教育万能主義
2-1 SF映画『ガタカ』
2-2 野生児
2-3 隔離ザルの異常行動からの回復
2-4 社会的隔離児の発達遅滞とその回復
2-5 被虐待児の回復
2-6 刺激が剥奪された環境 ― クレーシュ
4-1 安定感と探索
4-2 モデリングによる能動的学習
4-3 フレネ学校での文字の学習
4-4 能動的な学び ―『学校』
4-5 ないところに応答的環境を作り出す
―『ライフ・イズ・ビューティフル
4-6 大人の指導の必要性 ―『リトル・ダンサー』
4-7 なぜ2人の少年は立ち直ったのか ―『学校?』
7-1 「好き放題」は楽しいか? ―『いやいやえん』の場合
7-2 少年の自治の結末
―『蝿の王』と『芽むしり 仔撃ち』の場合
7-3 『滝山コミューン1974』
7-4 なぜ掃除当番をしなくてはいけないのか?
7-5 『小さなテツガクシャたち』― 杉本治くんの例
8-1 父親による息子殺害事件
10-1 教室が私に未来を与えてくれた
10-2 『希望の国のエクソダス』―「希望だけがない」
日本という国で生きる中学生たち
10-3 自己確認型の非行
10-4 高村智恵子と高村光太郎の場合
10-5 『エイブル able』― 知的障害者の達成
10-6 老人と少年の交流 ―『博士の愛した数式』と『夏の庭
10-7 老人ホーム入居者の健康度
10-8 『100万回生きたねこ』
10-9 ユダヤ人収容所での精神衛生実験
10-10 大河内くんの自殺
10-11 無条件の受容・肯定に支えられる ―『まゆみのマーチ』
11-1 村上春樹の執筆活動維持についてのメタ認知
11-2 いじめにどう対処するか ―『セッちゃん』
装幀=加藤俊二
はじめに
教育心理学とはどういう学問か、なぜ学ぶ必要があるのか
本書の概要
第I部 発達と教育
第1章 教育がもつ2つの側面と、現在の教育状況
1 教育がもつ2つの側面
2 2つの大人のかかわり方と教育状況の変遷
3 現代社会と主体的・能動的学び
第2章 発達における経験の重要性と発達の可塑性
1 発達における遺伝と環境
2 初期経験の重要性
3 人間の発達の特殊性
4 発達の可塑性 ― 初期経験の効果の持続性
第II部 発達・学習のとらえ方と学習の方法
第3章 大人主導の発達・学習・教育観 ― 行動主義の学習・教育観
1 学習成立の理論 ― 条件づけ
2 教育への応用(1)― プログラム学習
3 教育への応用(2)― 行動療法
第4章 子どもの能動性を重視する発達・学習・教育観
― ピアジェの発達・教育観
1 ピアジェの認知発達理論
2 ピアジェ理論から導かれる大人・教育の役割
3 子どもの能動性を重視する学習法
4 行動主義的考え方とピアジェ的考え方の比較、
および併用の必要性
第5章 子どもの能動性を考慮しつつ大人の働きかけを重視する発達・
学習・教育観 ― 認知心理学の立場
1 知識の構成化の理論
2 状況主義・状況的認知理論
第III部 道徳性・社会性の発達と教育
第6章 大人主導の道徳性発達の考え方
1 精神分析理論
2 社会的学習理論
3 日本の道徳教育への示唆
第7章 道徳性の認知発達理論 ― 子どもの能動性を重視する立場
1 ピアジェの道徳性発達の理論
2 コールバーグ理論
3 コールバーグ以後の理論と日本の教育への示唆
第8章 道徳性・社会性の発達における大人の役割 ― 望ましくない行動
への対処
第IV部 自己学習を可能にするもの
第9章 内発的動機づけ
1 内発的動機づけ
2 内発的動機づけに基づく学習
第10章 自己効力感、有能感
1 自己効力感、有能感
2 原因帰属
3 無力感の獲得
4 現代青少年の無気力の原因
5 無力感の克服
第11章 メタ認知
1 自己制御学習
2 メタ認知
3 メタ認知の育成
おわりに
文献
索引
コラム
1-1 自主性の尊重と集団との軋轢
1-2 教育万能主義
2-1 SF映画『ガタカ』
2-2 野生児
2-3 隔離ザルの異常行動からの回復
2-4 社会的隔離児の発達遅滞とその回復
2-5 被虐待児の回復
2-6 刺激が剥奪された環境 ― クレーシュ
4-1 安定感と探索
4-2 モデリングによる能動的学習
4-3 フレネ学校での文字の学習
4-4 能動的な学び ―『学校』
4-5 ないところに応答的環境を作り出す
―『ライフ・イズ・ビューティフル
4-6 大人の指導の必要性 ―『リトル・ダンサー』
4-7 なぜ2人の少年は立ち直ったのか ―『学校?』
7-1 「好き放題」は楽しいか? ―『いやいやえん』の場合
7-2 少年の自治の結末
―『蝿の王』と『芽むしり 仔撃ち』の場合
7-3 『滝山コミューン1974』
7-4 なぜ掃除当番をしなくてはいけないのか?
7-5 『小さなテツガクシャたち』― 杉本治くんの例
8-1 父親による息子殺害事件
10-1 教室が私に未来を与えてくれた
10-2 『希望の国のエクソダス』―「希望だけがない」
日本という国で生きる中学生たち
10-3 自己確認型の非行
10-4 高村智恵子と高村光太郎の場合
10-5 『エイブル able』― 知的障害者の達成
10-6 老人と少年の交流 ―『博士の愛した数式』と『夏の庭
10-7 老人ホーム入居者の健康度
10-8 『100万回生きたねこ』
10-9 ユダヤ人収容所での精神衛生実験
10-10 大河内くんの自殺
10-11 無条件の受容・肯定に支えられる ―『まゆみのマーチ』
11-1 村上春樹の執筆活動維持についてのメタ認知
11-2 いじめにどう対処するか ―『セッちゃん』
装幀=加藤俊二