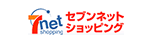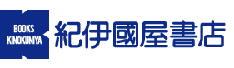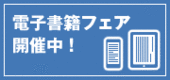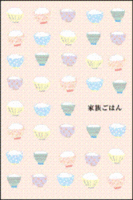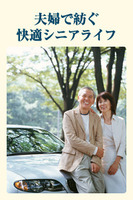こころの旅
発達心理学入門

| 著者 | 山岸 明子 著 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 発達・教育 |
| 出版年月日 | 2011/06/06 |
| ISBN | 9784788512375 |
| 判型・ページ数 | A5・184ページ |
| 定価 | 本体1,900円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
文学や映画に描かれた具体的な人間の姿をとりあげて,胎児の時から老人になるまで,心が一生をかけてたどる旅を発達心理学の視点から描く。実際の人生の文脈をとおして発達心理学の理論や基本的概念が楽しく学べるように工夫されたテキスト。
こころの旅――目次
まえがき
第1章 発達とは何か、発達心理学とは何か
1 発達心理学とは何か
2 発達心理学を学ぶ意義
3 発達とは何か
第2章 発達を規定するもの
1 発達における遺伝と環境
2 発達初期の経験の重要性
3 発達の可塑性 ― 発達初期の経験の効果の持続性
4 文化の重要性
第3章 乳児期 ― 母子関係の成立
1 有能な赤ちゃん
2 母子関係の成立
3 基本的信頼感
4 アタッチメント(愛着)
5 母子関係を規定するもの
第4章 幼児期 ― 自立の時期
1 自我の芽生え
2 幼児前期の発達課題 ― 自律性 対 恥・疑惑
3 自立性の発達
第5章 乳幼児期 ― その様々な発達
1 運動能力の発達
2 ことばの発達
3 認知の発達
4 遊びの発達
5 対人関係の発達
第6章 児童期
1 知的能力の発達
2 社会性の発達
3 自我の発達
4 大人との関係
5 現代社会の児童期の問題
第7章 青年期
1 青年期におこる変化
2 自我同一性をめぐる葛藤と発達課題
3 青年期の対人関係
4 現代青年の問題行動
第8章 成人期、そして老年期
1 初期成人期
2 成人期(中年期、壮年期)
3 老年期(老人期)
補章 発達障害
1 発達障害とは
2 広汎性発達障害
3 学習障害
4 ADHD(注意欠陥多動性障害)
あとがき
文献
索引
コラム
1-1 まわり道とこころの旅
1-2 エリクソンの生涯
2-1 隔離サルの異常行動とその回復
2-2 社会的隔離児の発達遅滞とその回復
2-3 刺激が剥奪された環境 ― クレーシュ
2-4 被虐待児の回復 ―『メItモ と呼ばれた子』
2-5 集団行動と国民性
3-1 子につらくあたる母親と幼少期の経験
3-2 育てにくい子の子育て
4-1 歩けることの喜び ― 童謡「春よ来い」
4-2 自己鏡像への反応
5-1 自己中心性の例(親族の名称)
5-2 幼児にとってのよい子 & 愛着対象との別れ ―「約束」
5-3 トラウマと遊び ―『禁じられた遊び』
5-4 子育てを担う父親 ―『クレイマー、クレイマー』
5-5 感情の発達
5-6 暴力的な6歳児の事例
6-1 生産性課題を目指した連帯 ―『エーミールと探偵たち』
6-2 前思春期のチャム ― 羽仁進少年と『赤毛のアン』
6-3 ギャング・エイジの少年たち ―『スタンド・バイ・ミー』
6-4 小児がんの直也くんの生産性課題
6-5 少年を支える空想上の友人 ―『いけちゃんとぼく』
7-1 性の目覚め ―『北の国から』
7-2 思春期の心理 ― 石川啄木・『アンネの日記』『愛を読むひと』
7-3 同一性拡散 ― 村上春樹の小説
7-4 同一性拡散から否定的同一性へ ―『青い春』
7-5 子離れできない母 ―『海辺の光景』
7-6 相手にあわせて演技する高校生
7-7 恋愛のむずかしさ
7-8 『死刑でいいです ― 孤立が生んだ2つの殺人』
8-1 母子相互作用で使われる技法
8-2 『ネグレクト』― それをもたらした要因
8-3 被虐待からの立ち直り
8-4 アイデンティティの問い直し ― 齋藤茂吉の歌
8-5 村上春樹の作品に描かれた成人期の発達課題
8-6 「折々のうた」にみる成人期の発達課題
8-7 神谷美恵子と生殖性課題
8-8 老年期の人生の受容 ―『トト・ザ・ヒーロー』
8-9 老年期の危機と回復 ―『アバウト・シュミット』
補-1 「トットちゃん」と「こうた」の行動と大人の対処
装幀=難波園子
まえがき
第1章 発達とは何か、発達心理学とは何か
1 発達心理学とは何か
2 発達心理学を学ぶ意義
3 発達とは何か
第2章 発達を規定するもの
1 発達における遺伝と環境
2 発達初期の経験の重要性
3 発達の可塑性 ― 発達初期の経験の効果の持続性
4 文化の重要性
第3章 乳児期 ― 母子関係の成立
1 有能な赤ちゃん
2 母子関係の成立
3 基本的信頼感
4 アタッチメント(愛着)
5 母子関係を規定するもの
第4章 幼児期 ― 自立の時期
1 自我の芽生え
2 幼児前期の発達課題 ― 自律性 対 恥・疑惑
3 自立性の発達
第5章 乳幼児期 ― その様々な発達
1 運動能力の発達
2 ことばの発達
3 認知の発達
4 遊びの発達
5 対人関係の発達
第6章 児童期
1 知的能力の発達
2 社会性の発達
3 自我の発達
4 大人との関係
5 現代社会の児童期の問題
第7章 青年期
1 青年期におこる変化
2 自我同一性をめぐる葛藤と発達課題
3 青年期の対人関係
4 現代青年の問題行動
第8章 成人期、そして老年期
1 初期成人期
2 成人期(中年期、壮年期)
3 老年期(老人期)
補章 発達障害
1 発達障害とは
2 広汎性発達障害
3 学習障害
4 ADHD(注意欠陥多動性障害)
あとがき
文献
索引
コラム
1-1 まわり道とこころの旅
1-2 エリクソンの生涯
2-1 隔離サルの異常行動とその回復
2-2 社会的隔離児の発達遅滞とその回復
2-3 刺激が剥奪された環境 ― クレーシュ
2-4 被虐待児の回復 ―『メItモ と呼ばれた子』
2-5 集団行動と国民性
3-1 子につらくあたる母親と幼少期の経験
3-2 育てにくい子の子育て
4-1 歩けることの喜び ― 童謡「春よ来い」
4-2 自己鏡像への反応
5-1 自己中心性の例(親族の名称)
5-2 幼児にとってのよい子 & 愛着対象との別れ ―「約束」
5-3 トラウマと遊び ―『禁じられた遊び』
5-4 子育てを担う父親 ―『クレイマー、クレイマー』
5-5 感情の発達
5-6 暴力的な6歳児の事例
6-1 生産性課題を目指した連帯 ―『エーミールと探偵たち』
6-2 前思春期のチャム ― 羽仁進少年と『赤毛のアン』
6-3 ギャング・エイジの少年たち ―『スタンド・バイ・ミー』
6-4 小児がんの直也くんの生産性課題
6-5 少年を支える空想上の友人 ―『いけちゃんとぼく』
7-1 性の目覚め ―『北の国から』
7-2 思春期の心理 ― 石川啄木・『アンネの日記』『愛を読むひと』
7-3 同一性拡散 ― 村上春樹の小説
7-4 同一性拡散から否定的同一性へ ―『青い春』
7-5 子離れできない母 ―『海辺の光景』
7-6 相手にあわせて演技する高校生
7-7 恋愛のむずかしさ
7-8 『死刑でいいです ― 孤立が生んだ2つの殺人』
8-1 母子相互作用で使われる技法
8-2 『ネグレクト』― それをもたらした要因
8-3 被虐待からの立ち直り
8-4 アイデンティティの問い直し ― 齋藤茂吉の歌
8-5 村上春樹の作品に描かれた成人期の発達課題
8-6 「折々のうた」にみる成人期の発達課題
8-7 神谷美恵子と生殖性課題
8-8 老年期の人生の受容 ―『トト・ザ・ヒーロー』
8-9 老年期の危機と回復 ―『アバウト・シュミット』
補-1 「トットちゃん」と「こうた」の行動と大人の対処
装幀=難波園子