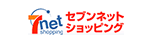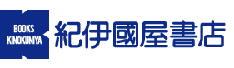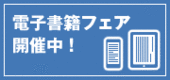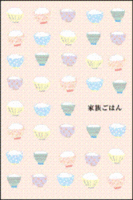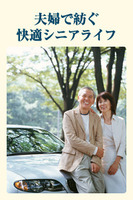主題としての〈終り〉
文学の構想力
小説はなぜ終るのか。ひとは〈終り〉を仮構することで世界を意味づけようとする。二葉亭四迷の〈終り〉,夏目漱石の〈終り〉,探偵小説の〈終り〉,一人称小説の〈終り〉など,さまざまな〈終り〉をめぐる欲望を,テクストのおかれた場所で問うスリリングな論考。
主題としての〈終り〉─目次
第一部 主題としての〈終り〉
第一章 消し去られた〈終り〉――二葉亭四迷『浮雲』(1)
一 消し去られた「(終)」
二 受け容れられる〈終り〉
三 拒否される〈終り〉/〈モード〉としての自然主義
第二章 〈未完〉の成立――二葉亭四迷『浮雲』(2)
一 二葉亭の死
二 〈未完〉の成立
三 完結する〈未完〉
四 近代主体論的な〈終り〉
第三章 〈終り〉をめぐる政治学――二葉亭四迷『浮雲』(3)
一 解釈される〈終り〉
二 実証される〈終り〉
三 『浮雲』的な〈終り〉にむけて
第四章 探偵小説の〈終り〉――森田思軒訳『探偵ユーベル』
一 問題の発端
二 「周密訳」をめぐって
三 ユゴーの受容
四 「探偵小説」というあり方
第五章 同時代的な想像力と〈終り〉――徳冨蘆花『不如帰』
一 方法としてのメタファー
二 越境しない語り
三 片づけられた〈終り〉
第六章 オープンエンドという〈終り〉――夏目漱石『明暗』
一 大団円的な〈終り〉
二 オープンエンドという〈終り〉
三 漱石的な〈終り〉
四 『明暗』の〈終り〉に向けて
第二部 〈終り〉をめぐる断章
第一章 三人称的な〈終り〉の模索――坪内逍遙訳『贋貨つかひ』
一 物語の枠
二 〈人称〉の翻訳
三 言語交通としての〈翻訳〉
第二章 韜晦する〈終り〉――二葉亭四迷『平凡』
一 自然主義と『平凡』
二 語りと「描写」
三 教科書のなかの『平凡』
四 『平凡』の〈終り〉
第三章 勧善懲悪小説的な〈終り〉――夏目漱石『虞美人草』
一 「勧善懲悪」という枠組み
二 アレゴリー小説としての『虞美人草』
三 『虞美人草』の結末
第四章 〈暴力〉小説の結末――芥川龍之介『藪の中』
一 〈物語〉の〈場〉
二 〈藪の中〉の〈暴力〉
三 閉じられる〈眼差し〉
第五章 〈痕跡〉としての「山節」――深沢七郎『山節考』
一 作られた「民話」
二 「潜勢力」としての「山節」
三 物語の〈場〉としての「山節」
第六章 一人称小説の〈終り〉――村上春樹『ノルウェイの森』
一 自己療養としての語り
二 意匠としての語り
三 切断と結合
四 脱=中心化された〈終り〉
注
あとがき
初出一覧
索引
装幀=難波園子
第一部 主題としての〈終り〉
第一章 消し去られた〈終り〉――二葉亭四迷『浮雲』(1)
一 消し去られた「(終)」
二 受け容れられる〈終り〉
三 拒否される〈終り〉/〈モード〉としての自然主義
第二章 〈未完〉の成立――二葉亭四迷『浮雲』(2)
一 二葉亭の死
二 〈未完〉の成立
三 完結する〈未完〉
四 近代主体論的な〈終り〉
第三章 〈終り〉をめぐる政治学――二葉亭四迷『浮雲』(3)
一 解釈される〈終り〉
二 実証される〈終り〉
三 『浮雲』的な〈終り〉にむけて
第四章 探偵小説の〈終り〉――森田思軒訳『探偵ユーベル』
一 問題の発端
二 「周密訳」をめぐって
三 ユゴーの受容
四 「探偵小説」というあり方
第五章 同時代的な想像力と〈終り〉――徳冨蘆花『不如帰』
一 方法としてのメタファー
二 越境しない語り
三 片づけられた〈終り〉
第六章 オープンエンドという〈終り〉――夏目漱石『明暗』
一 大団円的な〈終り〉
二 オープンエンドという〈終り〉
三 漱石的な〈終り〉
四 『明暗』の〈終り〉に向けて
第二部 〈終り〉をめぐる断章
第一章 三人称的な〈終り〉の模索――坪内逍遙訳『贋貨つかひ』
一 物語の枠
二 〈人称〉の翻訳
三 言語交通としての〈翻訳〉
第二章 韜晦する〈終り〉――二葉亭四迷『平凡』
一 自然主義と『平凡』
二 語りと「描写」
三 教科書のなかの『平凡』
四 『平凡』の〈終り〉
第三章 勧善懲悪小説的な〈終り〉――夏目漱石『虞美人草』
一 「勧善懲悪」という枠組み
二 アレゴリー小説としての『虞美人草』
三 『虞美人草』の結末
第四章 〈暴力〉小説の結末――芥川龍之介『藪の中』
一 〈物語〉の〈場〉
二 〈藪の中〉の〈暴力〉
三 閉じられる〈眼差し〉
第五章 〈痕跡〉としての「山節」――深沢七郎『山節考』
一 作られた「民話」
二 「潜勢力」としての「山節」
三 物語の〈場〉としての「山節」
第六章 一人称小説の〈終り〉――村上春樹『ノルウェイの森』
一 自己療養としての語り
二 意匠としての語り
三 切断と結合
四 脱=中心化された〈終り〉
注
あとがき
初出一覧
索引
装幀=難波園子