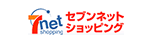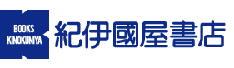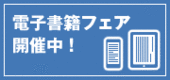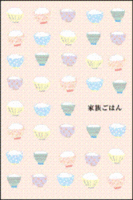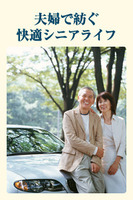あたりまえを疑え!
臨床教育学入門

| 著者 | 遠藤野ゆり 著 大塚 類 著 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 発達・教育 |
| 出版年月日 | 2014/04/15 |
| ISBN | 9784788513761 |
| 判型・ページ数 | 4-6・200ページ |
| 定価 | 本体1,800円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
これがフツー,あたりまえと思っていることも,見る視点,立場によってビックリするほど違う。家庭や社会,学校における重要な教育問題をとおして常識に挑戦し,現実,他者,自分を「どのよう〈に〉見るか」を鍛える,まったく新しい臨床教育学入門。
あたりまえを疑え!――目次
序 文(筒井美紀)
まえがき
序 章 みんなと普通に生きられること
─〈枠組み〉としてのあたりまえ
序-1 普通とかみんなとかって何だろう
序-2 責任を免除してくれる世間
序-3 2つの物語
第?部 現実はどう理解されるの?
第1章 家族の形─データから確かめる
1-1 家族をめぐるさまざまな問題の基礎知識
1-1-1 子どもの貧困と学力
1-1-2 離婚件数と離婚率
1-1-3 ひとり親世帯
1-1-4 親になれない親─モンスターペアレント
1-2 曖昧な〈標準〉と統計資料
1-2-1 みんなきっとそう思うはず
1-2-2 標準世帯
1-2-3 少子化とひとりっ子
1-3 多様化する家族と問題の捉えなおし
1-3-1 〈標準〉は何のため?
1-3-2 本当に「モンスター」?
第2章 児童虐待─立場の違いを捉える
2-1 児童虐待についての基礎知識
2-1-1 児童虐待の定義
2-1-2 通告の義務
2-1-3 児童虐待の相談対応件数から読みとれること
2-2 視点によって見えてくる世界の違い
2-2-1 創りだされた世界
2-2-2 児童虐待は本当に増えたのか
2-3 虐待する親はモンスターなのか?
2-3-1 愛していても虐待をしてしまう
2-3-2 虐待の〈世代連鎖〉
第3章 発達障害─多様に知覚し認知する
3-1 発達障害の基礎知識
3-1-1 発達障害の定義
3-2 発達障害における認知の優位性
3-2-1 聴覚優位と視覚優位
3-2-2 その他の優位性─線と色
3-3 知覚に由来する生きづらさ
3-3-1 視覚
3-3-2 聴覚
3-3-3 味覚
3-3-4 触覚
3-3-5 嗅覚
3-3-6 〈正常〉と〈異常〉の境目
第4章 生きられる時空間─世界を信頼して生きる
4-1 時間感覚・空間感覚の基礎知識
4-1-1 方向感覚と空間感覚
4-1-2 時間感覚
4-1-3 時空間の身体感覚からくる生きづらさ
4-2 生きられる時空間
4-2-1 生きられる空間─根をおろして住まう
4-2-2 生きられる時間─意味づけて分節化する
4-3 生きられる時空間と私たちの生
4-3-1 生きられる空間にまつわる不安
4-3-2 生きられる時間にまつわる不安
4-3-3 時空間の安らぐ場所としての〈居場所〉
第?部 他者はどう理解できるの?
第5章 いじめ─雰囲気を共に生きる
5-1 いじめの基礎知識
5-1-1 いじめ防止対策推進法の概要
5-1-2 これまでのいじめ論
5-1-3 新しいいじめ論 ・ スクールカースト
5-1-4 新しいいじめ論 ・ 優しい関係
5-1-5 新しいいじめ論 ・ 群生秩序
5-2 感情と雰囲気に関する現象学の知見
5-2-1 雰囲気としての感情
5-2-2 雰囲気に基づく他者理解
5-3 いじめ再考
5-3-1 被害者原因論
5-3-2 気づかないうちに強要されているいじめ
5-3-3 後づけされる理由
5-3-4 加害者が味わう〈理不尽さ〉
第6章 自閉症スペクトラム障害─相手の気もちを理解する
6-1 自閉症の基礎知識
6-1-1 自閉症をめぐる定義
6-1-2 自閉症スペクトラム障害の特徴
6-2 感情移入論
6-2-1 フッサールによる一方向的な感情移入
6-2-2 浸透的で双方向的な感情移入
6-3 相手の気もちが理解できないつらさ
6-3-1 気もちがわからないからこその衝撃
6-3-2 感じとってもどうにもできない〈ズレ〉
第7章 カウンセリング─内なる声を聴く
7-1 学校におけるケア職についての基礎知識
7-2 カウンセリング
7-2-1 カウンセリングの定義
7-2-2 傾聴
7-3 傾聴のむずかしさと可能性
7-3-1 傾聴は誰にでもできる?
7-3-2 カウンセラーの苦悩
第?部 自己をどう理解するの?
第8章 不登校─語ることで自己をつくる
8-1 不登校の基礎知識
8-1-1 不登校の定義と該当者数の推移
8-1-2 不登校に関する法律的な問題
8-1-3 不登校をどう捉えるか
8-1-4 不登校者の進路とひきこもり
8-2 ナラティヴ・アプローチ
8-2-1 セオリーとナラティヴ
8-2-2 特定の立場からの物語とドミナント・ストーリー
8-2-3 語ることが自己をつくる
8-3 不登校のナラティヴ
8-3-1 不登校者自身の語り
8-3-2 非不登校者は何を語るのか
第9章 非行─自分をふり返り反省する
9-1 非行についての基礎知識
9-1-1 非行の定義
9-1-2 非行件数の推移
9-1-3 非行への対応
9-2 反省とはどのようなことか
9-2-1 思い出すことを可能にするもの
─自己についての半透明の意識
9-2-2 反省の無限ループ
9-3 希望につなげる反省は可能か
9-3-1 反省指導において起きること
9-3-2 反省の絶望を超えて
第10章 キャリア教育─存在を肯われて生き方を選ぶ
10-1 キャリア教育の基礎知識
10-1-1 キャリア教育の定義
10-1-2 産業構造の変化
10-1-3 意識や資質をめぐる問題
10-1-4 キャリア教育の問題
10-2 自尊感情
10-2-1 自尊感情の意味とジェームズの定義
10-2-2 ローゼンバーグの自尊感情尺度
10-2-3 基本的自尊感情と社会的自尊感情
10-2-4 基本的自尊感情─存在の肯い
10-2-5 基本的自尊感情と社会的自尊感情のバランス
10-3 自尊感情と自己選択
10-3-1 なりたいもの探しの落とし穴
10-3-2 理不尽な社会における自己選択とキャリア教育
終 章 みんなと普通に生きつづけること
─〈基盤〉としてのあたりまえ
終-1 〈基盤〉としてのあたりまえ
終-2 あたりまえだと思えなくなるとき
終-3 あたりまえを疑うことができるのは
あとがき
引用・参考文献
索引
装幀=荒川伸生
序 文(筒井美紀)
まえがき
序 章 みんなと普通に生きられること
─〈枠組み〉としてのあたりまえ
序-1 普通とかみんなとかって何だろう
序-2 責任を免除してくれる世間
序-3 2つの物語
第?部 現実はどう理解されるの?
第1章 家族の形─データから確かめる
1-1 家族をめぐるさまざまな問題の基礎知識
1-1-1 子どもの貧困と学力
1-1-2 離婚件数と離婚率
1-1-3 ひとり親世帯
1-1-4 親になれない親─モンスターペアレント
1-2 曖昧な〈標準〉と統計資料
1-2-1 みんなきっとそう思うはず
1-2-2 標準世帯
1-2-3 少子化とひとりっ子
1-3 多様化する家族と問題の捉えなおし
1-3-1 〈標準〉は何のため?
1-3-2 本当に「モンスター」?
第2章 児童虐待─立場の違いを捉える
2-1 児童虐待についての基礎知識
2-1-1 児童虐待の定義
2-1-2 通告の義務
2-1-3 児童虐待の相談対応件数から読みとれること
2-2 視点によって見えてくる世界の違い
2-2-1 創りだされた世界
2-2-2 児童虐待は本当に増えたのか
2-3 虐待する親はモンスターなのか?
2-3-1 愛していても虐待をしてしまう
2-3-2 虐待の〈世代連鎖〉
第3章 発達障害─多様に知覚し認知する
3-1 発達障害の基礎知識
3-1-1 発達障害の定義
3-2 発達障害における認知の優位性
3-2-1 聴覚優位と視覚優位
3-2-2 その他の優位性─線と色
3-3 知覚に由来する生きづらさ
3-3-1 視覚
3-3-2 聴覚
3-3-3 味覚
3-3-4 触覚
3-3-5 嗅覚
3-3-6 〈正常〉と〈異常〉の境目
第4章 生きられる時空間─世界を信頼して生きる
4-1 時間感覚・空間感覚の基礎知識
4-1-1 方向感覚と空間感覚
4-1-2 時間感覚
4-1-3 時空間の身体感覚からくる生きづらさ
4-2 生きられる時空間
4-2-1 生きられる空間─根をおろして住まう
4-2-2 生きられる時間─意味づけて分節化する
4-3 生きられる時空間と私たちの生
4-3-1 生きられる空間にまつわる不安
4-3-2 生きられる時間にまつわる不安
4-3-3 時空間の安らぐ場所としての〈居場所〉
第?部 他者はどう理解できるの?
第5章 いじめ─雰囲気を共に生きる
5-1 いじめの基礎知識
5-1-1 いじめ防止対策推進法の概要
5-1-2 これまでのいじめ論
5-1-3 新しいいじめ論 ・ スクールカースト
5-1-4 新しいいじめ論 ・ 優しい関係
5-1-5 新しいいじめ論 ・ 群生秩序
5-2 感情と雰囲気に関する現象学の知見
5-2-1 雰囲気としての感情
5-2-2 雰囲気に基づく他者理解
5-3 いじめ再考
5-3-1 被害者原因論
5-3-2 気づかないうちに強要されているいじめ
5-3-3 後づけされる理由
5-3-4 加害者が味わう〈理不尽さ〉
第6章 自閉症スペクトラム障害─相手の気もちを理解する
6-1 自閉症の基礎知識
6-1-1 自閉症をめぐる定義
6-1-2 自閉症スペクトラム障害の特徴
6-2 感情移入論
6-2-1 フッサールによる一方向的な感情移入
6-2-2 浸透的で双方向的な感情移入
6-3 相手の気もちが理解できないつらさ
6-3-1 気もちがわからないからこその衝撃
6-3-2 感じとってもどうにもできない〈ズレ〉
第7章 カウンセリング─内なる声を聴く
7-1 学校におけるケア職についての基礎知識
7-2 カウンセリング
7-2-1 カウンセリングの定義
7-2-2 傾聴
7-3 傾聴のむずかしさと可能性
7-3-1 傾聴は誰にでもできる?
7-3-2 カウンセラーの苦悩
第?部 自己をどう理解するの?
第8章 不登校─語ることで自己をつくる
8-1 不登校の基礎知識
8-1-1 不登校の定義と該当者数の推移
8-1-2 不登校に関する法律的な問題
8-1-3 不登校をどう捉えるか
8-1-4 不登校者の進路とひきこもり
8-2 ナラティヴ・アプローチ
8-2-1 セオリーとナラティヴ
8-2-2 特定の立場からの物語とドミナント・ストーリー
8-2-3 語ることが自己をつくる
8-3 不登校のナラティヴ
8-3-1 不登校者自身の語り
8-3-2 非不登校者は何を語るのか
第9章 非行─自分をふり返り反省する
9-1 非行についての基礎知識
9-1-1 非行の定義
9-1-2 非行件数の推移
9-1-3 非行への対応
9-2 反省とはどのようなことか
9-2-1 思い出すことを可能にするもの
─自己についての半透明の意識
9-2-2 反省の無限ループ
9-3 希望につなげる反省は可能か
9-3-1 反省指導において起きること
9-3-2 反省の絶望を超えて
第10章 キャリア教育─存在を肯われて生き方を選ぶ
10-1 キャリア教育の基礎知識
10-1-1 キャリア教育の定義
10-1-2 産業構造の変化
10-1-3 意識や資質をめぐる問題
10-1-4 キャリア教育の問題
10-2 自尊感情
10-2-1 自尊感情の意味とジェームズの定義
10-2-2 ローゼンバーグの自尊感情尺度
10-2-3 基本的自尊感情と社会的自尊感情
10-2-4 基本的自尊感情─存在の肯い
10-2-5 基本的自尊感情と社会的自尊感情のバランス
10-3 自尊感情と自己選択
10-3-1 なりたいもの探しの落とし穴
10-3-2 理不尽な社会における自己選択とキャリア教育
終 章 みんなと普通に生きつづけること
─〈基盤〉としてのあたりまえ
終-1 〈基盤〉としてのあたりまえ
終-2 あたりまえだと思えなくなるとき
終-3 あたりまえを疑うことができるのは
あとがき
引用・参考文献
索引
装幀=荒川伸生