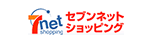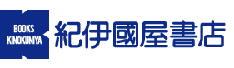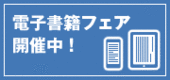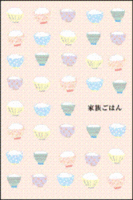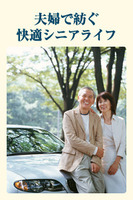日本語は映像的である
心理学から見えてくる日本語のしくみ

コミュニケーションの基本「共同注視」は,言語の成り立ちと密接につながっている。日本語に特徴的な主語の省略や敬語の多さを,共同注視の視点とそれに基づく映像的な特性から解き明かした,心理学にも言語学にも新しい見方を拓く刺激的な日本語論!
日本語は映像的である――目次
1章 日本語は映像的な言語である
日本語の基本特性
日本語と英語の違い
話し手・聞き手・共有映像の三項関係
三項関係と共同注意
自閉症児の場合
ことば以前からことばへ
2章 三項関係にもとづく「こそあど」の構造
共有する映像の位置
ここ・そこ・あそこの領域区分
英語の指示詞のあいまいさ
わかりにくい「here」と「there」
場の日本語と所有の英語
対象中心と行為者中心
自閉症者にとっての「こそあど」のわかりにくさ
現場指示から文脈指示へ
3章 日本語におけることばの省略
三項関係を前提としている日本語
『坊っちゃん』の書き出し
主語を欠くことができない英語
「アイ・ラブ・ユウ」はなかなか言えない
私とあなたを第三者のように表す英語
三項関係の内部視点と外部視点
英語圏の自閉症児
トンネルを抜けると雪国であった
書き手と読み手の視点
4章 「は」と「が」―映像の枠と要素の選択
共有映像の枠と中身
「私は山田です」と「私が山田です」
「は」と「が」の使い分けの始まり
「新情報・旧情報」説への疑問
映画に見られる映像文法
『桃太郎』の物語とクローズアップ機能
「the」と「a」に対応していない「は」と「が」の役割
映像文法の基本と変形
枠の強調と選択の強調
選択の追加と追加の取り消し
5章 「は」と「が」の組み合わせ
文には枠がなければならない
「象は鼻が長い」
「が」は「何が?」への答えである
選択肢としての格
枠の移動と自由な語順
移動カメラのような日本語の視点
「は」は文全体を支配する
映像的論理から意味的論理へ
日本語文の入れ子型構造
「面」の日本語と「点と線」の英語
6章 過去や未来への視点合わせ
〈いま・ここ〉にないものへの視点合わせ
情報の持ち主と文脈指示
「あの時」の共有性
聞き手への情報の引き渡し
どうして「その時 歴史が動いた」なのか?
未来に「あの時」は使えない
7章 視点移動とことばの組み立て
周辺から中心へ
日英の語順の違い
「図から地へ」と「地から図へ」
文化心理学からのアプローチ
SOV対SVO
日英の否定文の違い
固定視点と移動視点
俯瞰型と経過型
8章 共同注視者としての私とあなた
三項関係とウチ・ソトの文化
一・二人称の豊富さと三人称の乏しさ
普遍志向の英語の人称詞
基地としての私とあなた
尊敬語・謙譲語・丁寧語
自己対他者という二極的な見方への疑問
自己視点説と他者視点説への疑問
『タテ社会の人間関係』
私やあなたについて語るときの視点
彼/彼女の視点への同化
9章 日本語の臨場感・映像性
人の視界がもつ臨場感
カメラとオミヤゲの文化
写メールによる場の共有
俳句や短歌の形をしたオミヤゲ
オノマトペの豊富さ
日本語は点的言語か?
島国言語説を越えて
10章 世界の言語の中の日本語
特殊ではない日本語の文法
『「甘え」の構造』について
日本語と韓国語の類似性
三項関係への依拠と脱却
映像や文脈に依存しない文の構成法
膠着語・屈折語・孤立語と文の構成法
三項関係の視点からみた世界の言語
世界の言語に作用する両極的な力
日本語のアイデンティティ
あとがき
参考・引用文献
事項索引
人名索引
装幀 臼井新太郎装釘室
本文イラスト 熊谷 高幸
1章 日本語は映像的な言語である
日本語の基本特性
日本語と英語の違い
話し手・聞き手・共有映像の三項関係
三項関係と共同注意
自閉症児の場合
ことば以前からことばへ
2章 三項関係にもとづく「こそあど」の構造
共有する映像の位置
ここ・そこ・あそこの領域区分
英語の指示詞のあいまいさ
わかりにくい「here」と「there」
場の日本語と所有の英語
対象中心と行為者中心
自閉症者にとっての「こそあど」のわかりにくさ
現場指示から文脈指示へ
3章 日本語におけることばの省略
三項関係を前提としている日本語
『坊っちゃん』の書き出し
主語を欠くことができない英語
「アイ・ラブ・ユウ」はなかなか言えない
私とあなたを第三者のように表す英語
三項関係の内部視点と外部視点
英語圏の自閉症児
トンネルを抜けると雪国であった
書き手と読み手の視点
4章 「は」と「が」―映像の枠と要素の選択
共有映像の枠と中身
「私は山田です」と「私が山田です」
「は」と「が」の使い分けの始まり
「新情報・旧情報」説への疑問
映画に見られる映像文法
『桃太郎』の物語とクローズアップ機能
「the」と「a」に対応していない「は」と「が」の役割
映像文法の基本と変形
枠の強調と選択の強調
選択の追加と追加の取り消し
5章 「は」と「が」の組み合わせ
文には枠がなければならない
「象は鼻が長い」
「が」は「何が?」への答えである
選択肢としての格
枠の移動と自由な語順
移動カメラのような日本語の視点
「は」は文全体を支配する
映像的論理から意味的論理へ
日本語文の入れ子型構造
「面」の日本語と「点と線」の英語
6章 過去や未来への視点合わせ
〈いま・ここ〉にないものへの視点合わせ
情報の持ち主と文脈指示
「あの時」の共有性
聞き手への情報の引き渡し
どうして「その時 歴史が動いた」なのか?
未来に「あの時」は使えない
7章 視点移動とことばの組み立て
周辺から中心へ
日英の語順の違い
「図から地へ」と「地から図へ」
文化心理学からのアプローチ
SOV対SVO
日英の否定文の違い
固定視点と移動視点
俯瞰型と経過型
8章 共同注視者としての私とあなた
三項関係とウチ・ソトの文化
一・二人称の豊富さと三人称の乏しさ
普遍志向の英語の人称詞
基地としての私とあなた
尊敬語・謙譲語・丁寧語
自己対他者という二極的な見方への疑問
自己視点説と他者視点説への疑問
『タテ社会の人間関係』
私やあなたについて語るときの視点
彼/彼女の視点への同化
9章 日本語の臨場感・映像性
人の視界がもつ臨場感
カメラとオミヤゲの文化
写メールによる場の共有
俳句や短歌の形をしたオミヤゲ
オノマトペの豊富さ
日本語は点的言語か?
島国言語説を越えて
10章 世界の言語の中の日本語
特殊ではない日本語の文法
『「甘え」の構造』について
日本語と韓国語の類似性
三項関係への依拠と脱却
映像や文脈に依存しない文の構成法
膠着語・屈折語・孤立語と文の構成法
三項関係の視点からみた世界の言語
世界の言語に作用する両極的な力
日本語のアイデンティティ
あとがき
参考・引用文献
事項索引
人名索引
装幀 臼井新太郎装釘室
本文イラスト 熊谷 高幸