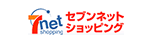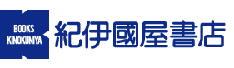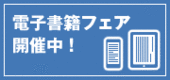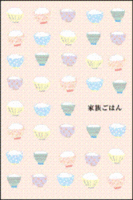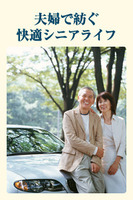新刊
チョムスキーの言語理論
その出発点から最新理論まで

変化と成長を続けているチョムスキー理論の出発点から現行理論に至るまでを,きわめて分かりやすく教えてくれる,他に類を見ない生成文法入門・活用書。内容を最大にアップデートした第三版から,政治観の章を除き,チョムスキーの言語理論に絞り翻訳。
チョムスキーの言語理論――目次
訳者まえがき
第3版への序文
再版への序文
初版への序文
序 論
1 チョムスキーの業績
2 妙想と影響
訳注
第1章 心の鏡
1 序 説
2 科学としての言語学
2.1 理想化の本質
2.2 コモンセンス
3 モジュール性
3.1 機能分離の二方向性
3.2 モジュールと準モジュール
3.3 知能と学習
4 言語能力と言語運用
4.1 言語能力と文法
4.2 規 則
4.3 I言語とE言語
5 言語運用、統語解析、そして語用論
5.1 統語解析的考察
5.2 語用論的考察
5.3 言語能力と言語運用 対 I言語とE言語
6 進化と生得性
6.1 言語獲得
6.2 刺激の貧困
6.3 語の意味
6.4 普遍性
7 自然言語と思考の言語
8 要 約
訳注
第2章 言語の基盤
1 序 説
1.1 何が達成されたか?─3つの妥当性
1.2 ミニマリスト・プログラム
2 言語の知識
2.1 レキシコン
2.2 構造の知識
2.3 構造関係の知識
3 記述的妥当性
3.1 形式的背景
3.2 表示レベル
3.3 構成素と規則
3.4 深層構造
3.5 記述 対 説明
4 説明的妥当性を目指して
4.1 規則から原理へ
4.2 句構造規則の廃止
4.3 Xバー理論
4.4 統率・束縛理論
4.5 変形の地位
4.6 原理とパラミタ
4.7 語彙範疇と機能範疇
5 説明的妥当性を越えて
5.1 ミニマリズム(極小主義)
5.2 スパルタ式言語学(Spartan linguistics)─ミニマリズムの成分
5.3 経済性
5.4 (実質上の)概念的必然性
5.5 第三要因の考慮
5.6 実 装
5.7 完璧な統語論
6 棚卸し─歴史的経過
6.1 進 化
6.2 第三要因
訳注
第3章 ことばと心理学
1 序 説
2 因果関係と説明
2.1 理論とデータ
2.2 行動主義
3 心理的実在性と証拠の性質
3.1 「心理学的」または「言語学的」証拠?
3.2 直 観
4 言語処理
4.1 複雑性の派生理論
4.2 文法と統語解析器
4.3 解析問題
4.4 経済性
5 言語獲得(プラトンの問題)
5.1 教えるのか、それとも教えられることなしに学ぶのか
5.2 学習か成長か
5.3 パラミタの設定
5.4 臨界期仮説
5.5 成 熟
6 言語病理
6.1 脳梁発達不全
6.2 多言語使用の天才
6.3 特異言語障害
7 行動主義者の反撃
7.1 コネクショニズム
7.2 構成主義と統計的学習
7.3 創発主義
8 結 論
訳注
第4章
哲学的実在論
─チョムスキーが与(くみ)する立場とそれをめぐる論争
1 序 説
2 チョムスキーが与する立場
2.1 心についての実在論
2.2 生得的構造
2.3 方法論的自然主義
2.4 再びI言語について
2.5 表示と演算
2.6 心理主義
2.7 合理主義と言語の知識
3 チョムスキーをめぐる論争
3.1 言語についての内在主義
3.2 言語についての外延主義的見解
3.3 言語とコミュニケーション
3.4 意味についての内在主義
3.5 生得性
3.6 心身問題
3.7 統一化と還元
4 結 論
訳注
原 注
文 献
人名索引
事項索引
装幀=新曜社デザイン室
訳者まえがき
第3版への序文
再版への序文
初版への序文
序 論
1 チョムスキーの業績
2 妙想と影響
訳注
第1章 心の鏡
1 序 説
2 科学としての言語学
2.1 理想化の本質
2.2 コモンセンス
3 モジュール性
3.1 機能分離の二方向性
3.2 モジュールと準モジュール
3.3 知能と学習
4 言語能力と言語運用
4.1 言語能力と文法
4.2 規 則
4.3 I言語とE言語
5 言語運用、統語解析、そして語用論
5.1 統語解析的考察
5.2 語用論的考察
5.3 言語能力と言語運用 対 I言語とE言語
6 進化と生得性
6.1 言語獲得
6.2 刺激の貧困
6.3 語の意味
6.4 普遍性
7 自然言語と思考の言語
8 要 約
訳注
第2章 言語の基盤
1 序 説
1.1 何が達成されたか?─3つの妥当性
1.2 ミニマリスト・プログラム
2 言語の知識
2.1 レキシコン
2.2 構造の知識
2.3 構造関係の知識
3 記述的妥当性
3.1 形式的背景
3.2 表示レベル
3.3 構成素と規則
3.4 深層構造
3.5 記述 対 説明
4 説明的妥当性を目指して
4.1 規則から原理へ
4.2 句構造規則の廃止
4.3 Xバー理論
4.4 統率・束縛理論
4.5 変形の地位
4.6 原理とパラミタ
4.7 語彙範疇と機能範疇
5 説明的妥当性を越えて
5.1 ミニマリズム(極小主義)
5.2 スパルタ式言語学(Spartan linguistics)─ミニマリズムの成分
5.3 経済性
5.4 (実質上の)概念的必然性
5.5 第三要因の考慮
5.6 実 装
5.7 完璧な統語論
6 棚卸し─歴史的経過
6.1 進 化
6.2 第三要因
訳注
第3章 ことばと心理学
1 序 説
2 因果関係と説明
2.1 理論とデータ
2.2 行動主義
3 心理的実在性と証拠の性質
3.1 「心理学的」または「言語学的」証拠?
3.2 直 観
4 言語処理
4.1 複雑性の派生理論
4.2 文法と統語解析器
4.3 解析問題
4.4 経済性
5 言語獲得(プラトンの問題)
5.1 教えるのか、それとも教えられることなしに学ぶのか
5.2 学習か成長か
5.3 パラミタの設定
5.4 臨界期仮説
5.5 成 熟
6 言語病理
6.1 脳梁発達不全
6.2 多言語使用の天才
6.3 特異言語障害
7 行動主義者の反撃
7.1 コネクショニズム
7.2 構成主義と統計的学習
7.3 創発主義
8 結 論
訳注
第4章
哲学的実在論
─チョムスキーが与(くみ)する立場とそれをめぐる論争
1 序 説
2 チョムスキーが与する立場
2.1 心についての実在論
2.2 生得的構造
2.3 方法論的自然主義
2.4 再びI言語について
2.5 表示と演算
2.6 心理主義
2.7 合理主義と言語の知識
3 チョムスキーをめぐる論争
3.1 言語についての内在主義
3.2 言語についての外延主義的見解
3.3 言語とコミュニケーション
3.4 意味についての内在主義
3.5 生得性
3.6 心身問題
3.7 統一化と還元
4 結 論
訳注
原 注
文 献
人名索引
事項索引
装幀=新曜社デザイン室