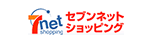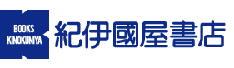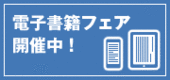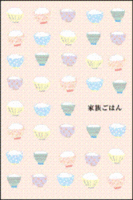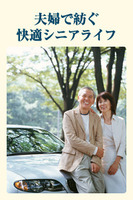日本の心理療法 身体篇

| 著者 | 秋田 巌 編 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 臨床 |
| シリーズ | 日本の心理療法 |
| 出版年月日 | 2017/02/10 |
| ISBN | 9784788514942 |
| 判型・ページ数 | A5・256ページ |
| 定価 | 本体3,200円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
西洋では挨拶場面での握手やハグなど身体接触は日常的だが,日本人にはあまり馴染みがない。そのような文化的背景を持つ日本でも受け入れられている,身体性と深く関わる「セラピー」を四つ取り上げ,こころの癒しをもたらす理由や仕組みを考察。
日本の心理療法 身体篇――目次
はじめに(各篇共通)
序
身体篇――わたしの自然をもとめて
第一章 臨床動作法と日本的心理療法 鶴 光代
日本で生まれた臨床動作法、その誕生と展開
●催眠法による脳性まひのひとの動きの改善 ●「動作」の概念と動作訓練
●自閉や多動の子どもへの動作訓練法の適用 ●「動作法」という概念の創出
●心理療法としての動作法 ●臨床動作法適用の広がりにみる日本的心理療法
●心理リハビリテイションとしての展開 ●心理リハビリテイションと日本人の心性
臨床動作法の技法――型から入り型から出る
●体験治療論と課題努力法 ●臨床動作法の考え方 ●動作療法の実際
●援助過程にみる型
日本文化にみる型と臨床動作法の型
●型について ●世阿弥にみる型 ●「守・破・離」について ●臨床動作法における型
第二章 和太鼓演奏における身体の体験
――皮膚感覚・運動感覚・深部感覚の心理臨床学的有用性 清源友香奈
はじめに
和太鼓演奏における身体の体験
●皮膚感覚の体験と体験の心理臨床学的有用性 ●運動感覚の体験と体験の心理臨床学的有用性
能動的でない運動感覚の体験について
●体性感覚の体験
自分で演奏するということの意味
体性感覚の体験の心理臨床学的有用性
●深部感覚の体験
身体の捉え方と身体感覚の位置づけ
深部感覚の体験の心理臨床学的有用性
語りとバウム
実存的身体心像――バウムの重さという視点
まとめ――身体感覚の心理臨床学的有用性
おわりに
第三章 歩き遍路の身体性――心理臨床への道程 北村香織
はじめに
遍路とはなにか
遍路の今昔
●癒しの時代
昨今のお遍路事情
歩き遍路の心理療法性
●日本的心理療法の特徴について ●身体とのつながり ●歩き遍路の身体性
●自然(しぜん/じねん)とのつながり ●人とのつながり
身体を生きる心理臨床
おわりに
第四章 気と身体――気のせいか、気のおかげか 濱野清志
はじめに
臨床心理学とは何か――一人称の科学の視点
イメージ体験としての気
私の身体について
気功からみた私の身体――鬆静自然
内丹における気――イメージ領域の身体を生む
この宇宙の座標軸の原点を創造する
王として立つこと …… 163
身体感覚体験の重視――気のせいと気のおかげ
音としての気――カキクケコの意味
身体篇――ディスカッション
おわりに
事項索引
人名索引
装幀=虎尾 隆
はじめに(各篇共通)
序
身体篇――わたしの自然をもとめて
第一章 臨床動作法と日本的心理療法 鶴 光代
日本で生まれた臨床動作法、その誕生と展開
●催眠法による脳性まひのひとの動きの改善 ●「動作」の概念と動作訓練
●自閉や多動の子どもへの動作訓練法の適用 ●「動作法」という概念の創出
●心理療法としての動作法 ●臨床動作法適用の広がりにみる日本的心理療法
●心理リハビリテイションとしての展開 ●心理リハビリテイションと日本人の心性
臨床動作法の技法――型から入り型から出る
●体験治療論と課題努力法 ●臨床動作法の考え方 ●動作療法の実際
●援助過程にみる型
日本文化にみる型と臨床動作法の型
●型について ●世阿弥にみる型 ●「守・破・離」について ●臨床動作法における型
第二章 和太鼓演奏における身体の体験
――皮膚感覚・運動感覚・深部感覚の心理臨床学的有用性 清源友香奈
はじめに
和太鼓演奏における身体の体験
●皮膚感覚の体験と体験の心理臨床学的有用性 ●運動感覚の体験と体験の心理臨床学的有用性
能動的でない運動感覚の体験について
●体性感覚の体験
自分で演奏するということの意味
体性感覚の体験の心理臨床学的有用性
●深部感覚の体験
身体の捉え方と身体感覚の位置づけ
深部感覚の体験の心理臨床学的有用性
語りとバウム
実存的身体心像――バウムの重さという視点
まとめ――身体感覚の心理臨床学的有用性
おわりに
第三章 歩き遍路の身体性――心理臨床への道程 北村香織
はじめに
遍路とはなにか
遍路の今昔
●癒しの時代
昨今のお遍路事情
歩き遍路の心理療法性
●日本的心理療法の特徴について ●身体とのつながり ●歩き遍路の身体性
●自然(しぜん/じねん)とのつながり ●人とのつながり
身体を生きる心理臨床
おわりに
第四章 気と身体――気のせいか、気のおかげか 濱野清志
はじめに
臨床心理学とは何か――一人称の科学の視点
イメージ体験としての気
私の身体について
気功からみた私の身体――鬆静自然
内丹における気――イメージ領域の身体を生む
この宇宙の座標軸の原点を創造する
王として立つこと …… 163
身体感覚体験の重視――気のせいと気のおかげ
音としての気――カキクケコの意味
身体篇――ディスカッション
おわりに
事項索引
人名索引
装幀=虎尾 隆