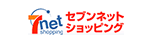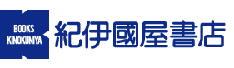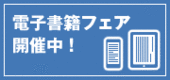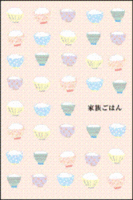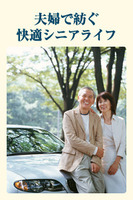フィールド心理学の実践
インターフィールドの冒険

| 著者 | 上淵 寿 編 フィールド解釈研究会 編 |
|---|---|
| ジャンル | 心理学・認知科学・臨床 > 概論・研究法 |
| 出版年月日 | 2013/09/05 |
| ISBN | 9784788513556 |
| 判型・ページ数 | A5・232ページ |
| 定価 | 本体2,500円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
研究者は何者としてフィールドに関わるのか? 生じているのは誰にとっての「問題」か? タテマエや方法論だけではすまない現場研究に戸惑い,悩み,悶える体験をインターフィールドの視点から掘り下げ,理論的・複眼的に考察。実践への示唆に満ちた書。
フィールド心理学の実践――目次
はしがき
序章 インターフィールド研究の実践 ───── 上淵 寿・本山方子
第?部 フィールドですれ違う
1章 「問題」を取り上げる
──「問題」とは何か? 誰にとっての問題か? ───── 磯村陸子
1.問題化によって可能になるもの
2.問題化が不可能にするもの
3.問題化がめざすもの
【ケース】あの時あれでよかったか
──保育カンファレンスからの省察 ───────── 野口隆子
1.初めての保育の場、A幼稚園との出会い
2.保育の場に参加した学生としての私
3.「ずれ」る──視点が違うことへの戸惑い
4.問いを問う
5.プロセスの中の私
6.おわりに──保育の場が「私」と「あの時」をどのように見ていたのか
2章 意味づけの功罪──人はつまずいて意味づけを行う ── 上淵 寿
1.質的研究における「意味づけ」の位置
2.意味づけに絡む要因の整理
3.研究者の「意味づけ」の効用と問題
4.「意味づけ」が困難な状況
5.フィールドを意味づける、フィールドに意味づけられる
6.肉体の意味づけ
7.とりあえず終わりに──意味づけはどこまでも …
【ケース】観察者が意味づけをためらうとき ────── 磯村陸子
1.ある出来事
2.誰かの行為を見ること
3.意味づけることと義務・責任
4.学校というフィールドで〈大人〉であること
5.おわりに
第?部 フィールドで生かされる
3章 見えることと共振のダイナミクス ───────── 松井愛奈
1.見ること、見えること
2.見えるとは?──幼稚園の観察事例から
3.見ようとすれば見えるようになるのか?
4.フィールドの実践に共振する
【ケース】日常をサバイヴするジェンダー実践
──かつて〈女子中学生〉だった私への共感 ───── 野坂祐子
1.はじめに
──「オネエサン」から「オバサン」に交差する視線の中で
2.フィールドをサバイヴする調査者
3.おわりに──フィールドにおける出会いの限界と可能性
4章 フィールドの狭間でもだえる自己
──自己論から他者論、そして身体論へ ────────── 上淵 寿
1.自己の二重性の問題
2.「研究者」としての私と「共同実践者」としての私
3.ポジション
4.ポジションから情動へ、身体へ
【ケース】「役に立つ」ことにこだわる〈私〉へのこだわり
──B幼稚園での動揺から ───────────── 掘越紀香
1.はじめに
2.「役に立つ」ことの難しさ
3.「役に立つ」ことへの〈私〉のこだわり
4.「役に立てない」ことに動揺した〈私〉の変化
5.「役に立つ」ことへのこだわりのサイクル
6.現在の「役に立つ」ことにこだわる〈私〉
7.結びにかえて──〈私〉へのこだわり
5章 「正義」の実践・実践の「正義」 ────────── 野坂祐子
1.はじめに──フィールドにおける「正義」の所在
2.正義の責任
3.正義の声──語られた言葉の重さと書ける言葉の軽さ
4.おわりに──「正義」を問うことの、その先へ
【ケース】学習を〈促す/妨げる〉デザイン
──地域の日本語教室を例にして ────────── 森下雅子
1.はじめに
2.学習環境のデザインとは
3.空間や道具のデザインの重要性
4.日本語教室A
5.日本語教室B
6.日本語教室C
7.日本語学習を促す学習環境とは
8.まとめ
6章 語られる局所性 ─────────────────── 上淵 寿
1.局所性と全体性
2.個別性・一般性
3.局所と共同体
4.おわりに
【ケース】子どもといる私のアクチュアリティと発現する局所性との間で
──────────── 古賀松香
1.フィールド研究における局所性の問題
2.感知される局所性の変化
3.語りの中で変化する局所性
4.研究者に求められる局所性に対する2つの認識
第?部 フィールドを味わいあう
7章 実践事例の記述と解釈の基盤 ─────────── 砂上史子
1.保育・教育の記録と解釈
2.複数の人間による解釈と了解の形成
3.解釈の違いに影響する立場
4.異なる実践現場の間での解釈の違い
【ケース】小学5年生の小集団学習事例の記述と解釈の実践
──観察当事者として ─────────────── 市川洋子
1.はじめに
2.取り上げた場面の決定プロセス
3.事例の記述と考察
4.掘越による事例記述と解釈を読んで
──違いが生じた理由とは?
【ケース】小学5年生の小集団学習事例の記述と解釈の実践
──第三者として ───────────────── 掘越紀香
1.筆者の戸惑いとスタンス
2.授業の全般的な印象と教師の対応
3.児童へのまなざし(主に男子Yについて)
4.調査者市川の事例と解釈を読んで
──「見つづける」ことと解釈妥当性
【メタ解釈】小学5年生の小集団学習事例の記述と解釈の実践
──2つのケース ───────────────── 砂上史子
1.知らないからこその詳細な記述
2.ビデオ映像の記述と解釈の妥当性
3.「らしさ」を捉える枠組み
4.解釈基盤の違い
5.まとめ──記述と解釈の内側と外側
8章 質的研究を読むこと・読まれること ─────── 本山方子
1.書き手─読み手─フィールド協力者のテクストを
媒介にした関係性
2.読むことと解釈共同体
3.読むことの個性
4.読むことの倫理
【ケース】麻生武著『身ぶりからことばへ』をめぐる読みの実践
──事例研究の説得力とは何か ─────────── 砂上史子
1.系の内側からの観察
2.麻生研究の記述と解釈
3.筆者の履歴と麻生研究の読み
4.麻生研究への問い
【ケース】麻生武著『身ぶりからことばへ』をめぐる読みの実践
──〈私〉による〈私たち〉の物語 ───────── 磯村陸子
1.本書の試み
2.共同的であるということ
3.〈私〉に埋め込まれた〈私たち〉
4.おわりに
【ケース】麻生武著『身ぶりからことばへ』をめぐる読みの実践
──誰が『身ぶりからことばへ』を書いたのか?─── 麻生 武
9章 インターフィールド実践としての教育
──心理学教育の立場から ─────────────── 上淵 寿
1.はじめに──高校生、受験生から、心理学専攻の大学生へ
2.「しろうと」から「くろうと」へ
3.研究するのは誰のためか
4.「くろうと」が学ぶこと
5.心理学における質的研究導入の問題
6.「研究とは何か」の理解について
人名索引
事項索引
装幀=虎尾 隆
はしがき
序章 インターフィールド研究の実践 ───── 上淵 寿・本山方子
第?部 フィールドですれ違う
1章 「問題」を取り上げる
──「問題」とは何か? 誰にとっての問題か? ───── 磯村陸子
1.問題化によって可能になるもの
2.問題化が不可能にするもの
3.問題化がめざすもの
【ケース】あの時あれでよかったか
──保育カンファレンスからの省察 ───────── 野口隆子
1.初めての保育の場、A幼稚園との出会い
2.保育の場に参加した学生としての私
3.「ずれ」る──視点が違うことへの戸惑い
4.問いを問う
5.プロセスの中の私
6.おわりに──保育の場が「私」と「あの時」をどのように見ていたのか
2章 意味づけの功罪──人はつまずいて意味づけを行う ── 上淵 寿
1.質的研究における「意味づけ」の位置
2.意味づけに絡む要因の整理
3.研究者の「意味づけ」の効用と問題
4.「意味づけ」が困難な状況
5.フィールドを意味づける、フィールドに意味づけられる
6.肉体の意味づけ
7.とりあえず終わりに──意味づけはどこまでも …
【ケース】観察者が意味づけをためらうとき ────── 磯村陸子
1.ある出来事
2.誰かの行為を見ること
3.意味づけることと義務・責任
4.学校というフィールドで〈大人〉であること
5.おわりに
第?部 フィールドで生かされる
3章 見えることと共振のダイナミクス ───────── 松井愛奈
1.見ること、見えること
2.見えるとは?──幼稚園の観察事例から
3.見ようとすれば見えるようになるのか?
4.フィールドの実践に共振する
【ケース】日常をサバイヴするジェンダー実践
──かつて〈女子中学生〉だった私への共感 ───── 野坂祐子
1.はじめに
──「オネエサン」から「オバサン」に交差する視線の中で
2.フィールドをサバイヴする調査者
3.おわりに──フィールドにおける出会いの限界と可能性
4章 フィールドの狭間でもだえる自己
──自己論から他者論、そして身体論へ ────────── 上淵 寿
1.自己の二重性の問題
2.「研究者」としての私と「共同実践者」としての私
3.ポジション
4.ポジションから情動へ、身体へ
【ケース】「役に立つ」ことにこだわる〈私〉へのこだわり
──B幼稚園での動揺から ───────────── 掘越紀香
1.はじめに
2.「役に立つ」ことの難しさ
3.「役に立つ」ことへの〈私〉のこだわり
4.「役に立てない」ことに動揺した〈私〉の変化
5.「役に立つ」ことへのこだわりのサイクル
6.現在の「役に立つ」ことにこだわる〈私〉
7.結びにかえて──〈私〉へのこだわり
5章 「正義」の実践・実践の「正義」 ────────── 野坂祐子
1.はじめに──フィールドにおける「正義」の所在
2.正義の責任
3.正義の声──語られた言葉の重さと書ける言葉の軽さ
4.おわりに──「正義」を問うことの、その先へ
【ケース】学習を〈促す/妨げる〉デザイン
──地域の日本語教室を例にして ────────── 森下雅子
1.はじめに
2.学習環境のデザインとは
3.空間や道具のデザインの重要性
4.日本語教室A
5.日本語教室B
6.日本語教室C
7.日本語学習を促す学習環境とは
8.まとめ
6章 語られる局所性 ─────────────────── 上淵 寿
1.局所性と全体性
2.個別性・一般性
3.局所と共同体
4.おわりに
【ケース】子どもといる私のアクチュアリティと発現する局所性との間で
──────────── 古賀松香
1.フィールド研究における局所性の問題
2.感知される局所性の変化
3.語りの中で変化する局所性
4.研究者に求められる局所性に対する2つの認識
第?部 フィールドを味わいあう
7章 実践事例の記述と解釈の基盤 ─────────── 砂上史子
1.保育・教育の記録と解釈
2.複数の人間による解釈と了解の形成
3.解釈の違いに影響する立場
4.異なる実践現場の間での解釈の違い
【ケース】小学5年生の小集団学習事例の記述と解釈の実践
──観察当事者として ─────────────── 市川洋子
1.はじめに
2.取り上げた場面の決定プロセス
3.事例の記述と考察
4.掘越による事例記述と解釈を読んで
──違いが生じた理由とは?
【ケース】小学5年生の小集団学習事例の記述と解釈の実践
──第三者として ───────────────── 掘越紀香
1.筆者の戸惑いとスタンス
2.授業の全般的な印象と教師の対応
3.児童へのまなざし(主に男子Yについて)
4.調査者市川の事例と解釈を読んで
──「見つづける」ことと解釈妥当性
【メタ解釈】小学5年生の小集団学習事例の記述と解釈の実践
──2つのケース ───────────────── 砂上史子
1.知らないからこその詳細な記述
2.ビデオ映像の記述と解釈の妥当性
3.「らしさ」を捉える枠組み
4.解釈基盤の違い
5.まとめ──記述と解釈の内側と外側
8章 質的研究を読むこと・読まれること ─────── 本山方子
1.書き手─読み手─フィールド協力者のテクストを
媒介にした関係性
2.読むことと解釈共同体
3.読むことの個性
4.読むことの倫理
【ケース】麻生武著『身ぶりからことばへ』をめぐる読みの実践
──事例研究の説得力とは何か ─────────── 砂上史子
1.系の内側からの観察
2.麻生研究の記述と解釈
3.筆者の履歴と麻生研究の読み
4.麻生研究への問い
【ケース】麻生武著『身ぶりからことばへ』をめぐる読みの実践
──〈私〉による〈私たち〉の物語 ───────── 磯村陸子
1.本書の試み
2.共同的であるということ
3.〈私〉に埋め込まれた〈私たち〉
4.おわりに
【ケース】麻生武著『身ぶりからことばへ』をめぐる読みの実践
──誰が『身ぶりからことばへ』を書いたのか?─── 麻生 武
9章 インターフィールド実践としての教育
──心理学教育の立場から ─────────────── 上淵 寿
1.はじめに──高校生、受験生から、心理学専攻の大学生へ
2.「しろうと」から「くろうと」へ
3.研究するのは誰のためか
4.「くろうと」が学ぶこと
5.心理学における質的研究導入の問題
6.「研究とは何か」の理解について
人名索引
事項索引
装幀=虎尾 隆