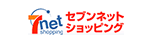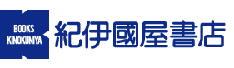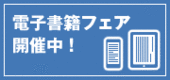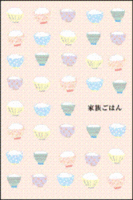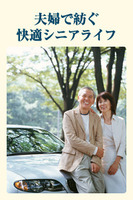〈移動〉と〈比較〉の日本帝国史
統治技術としての観光・博覧会・フィールドワーク

初期グローバリゼーション時代に可能になった「観光」「博覧会」「フィールドワーク」。植民地帝国を揺る,がすこれら,の〈比較〉実践は,学問と政策においていかに管理され体制を支えたのか。帝国期日本のナショナリズムの想像力と経験を問う。
〈移動〉と〈比較〉の日本帝国史――目次
序章 はじまりの拉致
第一章 理論視角――移動・比較・ナショナリズム
第一節 初期グローバリゼーションと帝国期日本のナショナリズム
第二節 ナショナリズム研究における「移動性」という視角
第一項 移動論的転回
第二項 旅と比較――B・アンダーソンのナショナリズム論
第三項 帝国の緊張
第三節 比較の帝国
第二章 「人類」から「東洋」へ――坪井正五郎の旅と比較
はじめに――旅する人類学者
第一節 身近なものを収集する――日本人類学における「比較」の縮小
第二節 「人類の理学」という構想――坪井正五郎による比較の手法と「人種」言説
第一項 「陳列」論――科学的な陳列とは何か
第二項 「分類」論――何のための分類か
第三項 「人種」論――黄禍論と進化論の争い
第三節 「東洋」の領土化――鳥居龍蔵の「東洋人種学」構想
第一項 人類学と人種学を分離する
第二項 人類から東洋へ――フィールドの限定と占有
第四節 「人類」学から「東洋人種」学へ
第三章 フィールドワークにおける「リスク」と「真正性」――鳥居龍蔵の台湾・西南中国調査
はじめに
第一節 リスクと真正性
第二節 一九世紀後半の海外フィールドワークの社会的基盤
第三節 孤独な観察者――学術探検と民族誌の創造
第四節 フィールドにおける「民族接触」と「異種混交性」――西南中国調査を中心に
第一項 危険な真実
第二項 風景と民族性
第三項 民族接触としての観察
第五節 「探検」という遺産
第四章 フィールドとしての博覧会――明治・大正期日本の原住民展示と人類学者
第一節 移動する村
第二節 明治・大正期日本の原住民展示――人類館を中心に
第三節 原住民展示の「学術性」――視覚・比較・一望監視装置
第四節 「見世物」化する展示、問い直される「真正性」
第五節 原住民展示の「真正性」――〈博覧会〉と〈フィールド〉の裂け目へ
小括
第五章 「台湾」表象をめぐる帝国の緊張129――第五回内国勧業博覧会における台湾館事業と内地観光事業
第一節 誤解の構造――植民地パビリオンの「文明/未開」図式を再考する
第二節 児玉・後藤統治時代の植民地経営の課題
第一項 台湾総督府の問題認識
第二項 台湾協会の問題認識
第三節 視覚教育としての博覧会――台湾館事業と内地観光事業の狙い
第四節 台湾館の成立過程
第一項 計画中止と代替計画
第二項 なぜ単独のパビリオンにこだわったのか――〈異域〉としての台湾
第五節 「帝国の緊張」の忘却
第六章 「比較」という統治技術――明治・大正期の先住民観光事業
はじめに
第一節 観光と先住民統治
第二節 明治・大正期の内地観光事業
第一項 権力を飼い馴らす――政策意図・参加者・目的地
第二項 観光と農耕民化政策
第三節 内地観光の衝撃
第一項 脅威としての日本
第二項 観光団という見世物
第三項 不平等の知覚
第七章 「比較」を管理する――霧社事件以後の先住民観光事業
第一節 観光と比較
第二節 観光地の選別――都市観光から農村観光へ
第一項 比較への無関心
第二項 行き過ぎた文明化
第三節 観光者の選別――老蕃から青年団へ
第四節 恥辱の埋め込み
第五節 「日本化」と「未開化」のダブルバインド――台湾博覧会の展示に注目して
第八章 フィールドワークとしての観光、メディアとしての民族――小山栄三の観光宣伝論と日本帝国の国際観光政策
はじめに
第一節 帝国と移動する人々――移民・観光・フィールドワーク
第二節 フィールドワークとしての観光
第三節 メディアとしての民族――外国人招請事業を手がかりに
第四節 民族接触と帝国秩序
第一項 接触領域の管理とナショナルな自己呈示
第二項 征服者の征服――境界侵犯への不安
第三項 帝国を循環させる
小括
第九章 「日本化」と「観光化」の狭間で――『民俗台湾』と日本民藝協会の台湾民藝保存運動
はじめに
第一節 ポスト・コロニアル時代の『民俗台湾』論争
第二節 戦時下台湾の自然・文化保存政策と『民俗台湾』
第三節 台湾民藝の骨董品化――「民藝解説」を中心に
第四節 『民俗台湾』と日本民藝協会の連帯
第五節 台湾民藝の「芸術性」と「歴史性」の相克
第六節 三つの「地方文化」構想
第七節 日本帝国史の脱中心化に向けて
結語 比較と植民地的想像力
年表 本書で扱った主な出来事
註
謝辞
参考文献一覧
索引
装幀=難波園子
序章 はじまりの拉致
第一章 理論視角――移動・比較・ナショナリズム
第一節 初期グローバリゼーションと帝国期日本のナショナリズム
第二節 ナショナリズム研究における「移動性」という視角
第一項 移動論的転回
第二項 旅と比較――B・アンダーソンのナショナリズム論
第三項 帝国の緊張
第三節 比較の帝国
第二章 「人類」から「東洋」へ――坪井正五郎の旅と比較
はじめに――旅する人類学者
第一節 身近なものを収集する――日本人類学における「比較」の縮小
第二節 「人類の理学」という構想――坪井正五郎による比較の手法と「人種」言説
第一項 「陳列」論――科学的な陳列とは何か
第二項 「分類」論――何のための分類か
第三項 「人種」論――黄禍論と進化論の争い
第三節 「東洋」の領土化――鳥居龍蔵の「東洋人種学」構想
第一項 人類学と人種学を分離する
第二項 人類から東洋へ――フィールドの限定と占有
第四節 「人類」学から「東洋人種」学へ
第三章 フィールドワークにおける「リスク」と「真正性」――鳥居龍蔵の台湾・西南中国調査
はじめに
第一節 リスクと真正性
第二節 一九世紀後半の海外フィールドワークの社会的基盤
第三節 孤独な観察者――学術探検と民族誌の創造
第四節 フィールドにおける「民族接触」と「異種混交性」――西南中国調査を中心に
第一項 危険な真実
第二項 風景と民族性
第三項 民族接触としての観察
第五節 「探検」という遺産
第四章 フィールドとしての博覧会――明治・大正期日本の原住民展示と人類学者
第一節 移動する村
第二節 明治・大正期日本の原住民展示――人類館を中心に
第三節 原住民展示の「学術性」――視覚・比較・一望監視装置
第四節 「見世物」化する展示、問い直される「真正性」
第五節 原住民展示の「真正性」――〈博覧会〉と〈フィールド〉の裂け目へ
小括
第五章 「台湾」表象をめぐる帝国の緊張129――第五回内国勧業博覧会における台湾館事業と内地観光事業
第一節 誤解の構造――植民地パビリオンの「文明/未開」図式を再考する
第二節 児玉・後藤統治時代の植民地経営の課題
第一項 台湾総督府の問題認識
第二項 台湾協会の問題認識
第三節 視覚教育としての博覧会――台湾館事業と内地観光事業の狙い
第四節 台湾館の成立過程
第一項 計画中止と代替計画
第二項 なぜ単独のパビリオンにこだわったのか――〈異域〉としての台湾
第五節 「帝国の緊張」の忘却
第六章 「比較」という統治技術――明治・大正期の先住民観光事業
はじめに
第一節 観光と先住民統治
第二節 明治・大正期の内地観光事業
第一項 権力を飼い馴らす――政策意図・参加者・目的地
第二項 観光と農耕民化政策
第三節 内地観光の衝撃
第一項 脅威としての日本
第二項 観光団という見世物
第三項 不平等の知覚
第七章 「比較」を管理する――霧社事件以後の先住民観光事業
第一節 観光と比較
第二節 観光地の選別――都市観光から農村観光へ
第一項 比較への無関心
第二項 行き過ぎた文明化
第三節 観光者の選別――老蕃から青年団へ
第四節 恥辱の埋め込み
第五節 「日本化」と「未開化」のダブルバインド――台湾博覧会の展示に注目して
第八章 フィールドワークとしての観光、メディアとしての民族――小山栄三の観光宣伝論と日本帝国の国際観光政策
はじめに
第一節 帝国と移動する人々――移民・観光・フィールドワーク
第二節 フィールドワークとしての観光
第三節 メディアとしての民族――外国人招請事業を手がかりに
第四節 民族接触と帝国秩序
第一項 接触領域の管理とナショナルな自己呈示
第二項 征服者の征服――境界侵犯への不安
第三項 帝国を循環させる
小括
第九章 「日本化」と「観光化」の狭間で――『民俗台湾』と日本民藝協会の台湾民藝保存運動
はじめに
第一節 ポスト・コロニアル時代の『民俗台湾』論争
第二節 戦時下台湾の自然・文化保存政策と『民俗台湾』
第三節 台湾民藝の骨董品化――「民藝解説」を中心に
第四節 『民俗台湾』と日本民藝協会の連帯
第五節 台湾民藝の「芸術性」と「歴史性」の相克
第六節 三つの「地方文化」構想
第七節 日本帝国史の脱中心化に向けて
結語 比較と植民地的想像力
年表 本書で扱った主な出来事
註
謝辞
参考文献一覧
索引
装幀=難波園子