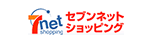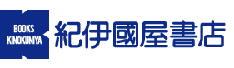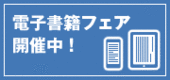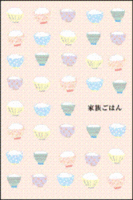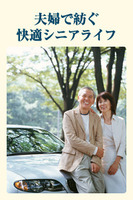現代日本人の中国像
日中国交正常化から天安門事件・天皇訪中まで

1970・80年代の友好・親中の時代から,いまや嫌中の時代。日中の絆はなぜ,いかにして失われたのか? 修復の手だては? 日本人の中国像の変容をたどりながら徹底検証する。若林正丈氏,船橋洋一氏,毛里和子氏などへの長時間インタビューも収録。
現代日本人の中国像――目次
本書を読まれる方へ
言説分析編
序 章 日本人の中国像の変遷――戦前、戦後、そして現代へ
一 日本人の中国像の解明――「市民外交」「国民世論」という視点から
二 「旧中国」から「新中国」へ
三 本書のねらいと時期区分
第一章 戦後日本人は文革の終わりをどう迎えたか 一九七三―七八年
――日中復交から平和条約締結まで
一 混迷する中国政治、足踏みする日中関係
二 脱文革・ポスト毛沢東の行方――批林批孔運動から第一次天安門事件へ
三 中米平和共存・中ソ対立・第三世界外交――「覇権条項」をめぐる国際情勢
四 台湾という視座
五 復縁から蜜月への兆し
第二章 友好と離反のはざまできしむ日中関係 一九七九―八七年
――中越戦争から民主化運動へ
一 高まる友好ムード、冷え込む論壇
二 視界不良の中ソ・中米関係
三 改革開放で露わになった中国の異質性
四 関心をひかなくなった中南海の政治動向
五 中国批判の根拠(一)――民主化を求める体制内外の声
六 中国批判の根拠(二)――香港からの情報と台湾からの世論工作
七 きしむ日中関係――対日「媚態外交」と対中「弱腰外交」
八 見失われてゆく紐帯の論理
第三章 天安門事件にいたる道 一九八八―九〇年
――日本から見た背景・経過・結末
一 日本からの天安門事件の眺め――当時と今と
二 事件の背景――五四運動の残響のなかで
三 事件の経過――愛国・民主から動乱・鎮圧へ
四 事件の結末――「国際的大気候」と「国内的小気候」
五 国家崩壊論と経済破綻論
第四章 天安門事件以後 反転する中国像 一九九一―九二年
一 経済制裁の継続か解除か
二 _小平最後の闘い――いかにV字回復はなされたか
三 浮足立つ香港、冷静保つ台湾
四 復交二〇年の日中関係修復から天皇訪中へ
五 天安門事件を背負って――中国の大国化と亡命者たち
六 反転する日中関係
第五章 戦後日本人の台湾像 一九四五年―現在
――対日情報・宣伝・世論工作との関連性をてがかりに
一 視界から消えた台湾
二 「以徳報怨」による道義外交の耐性
三 二度の台湾海峡危機――視界に入り始めた台湾および台湾人
四 日華断交――本格化する対日世論工作
五 日華関係から日台関係へ――対日世論工作の転換
六 形成されつつある対台湾認識経路
終 章 日本人の対中国認識経路を通して見た中国像
一 戦後―現代日本人の中国像 一九四五―九二年
二 同時代日本人の中国像 一九九〇年代―現在
三 対中認識経路をめぐる一〇のアスペクト
四 多彩な論者による豊かな中国像のために
補 章 戦後日本人のモンゴル像
――地政学的関心から文学的表象へ
一 戦前のモンゴル研究
二 敗戦によりフィールドを失ったモンゴル研究
三 異民族による中国征服王朝への関心
四 草原の非農耕騎馬遊牧民への郷愁
五 モンゴル独立への心情的加担
六 見失われたままの歴史的リアリティ
注
証言編
総解説 中国という巨大な客体を見すえて
1 若林正丈 歴史研究から同時代政治へ――台湾社会を見る目
2 西村成雄 変わりゆく中国に埋め込まれた歴史の地層を見据えて
3 濱下武志 地方・民間社会・南から見た中国の動態
4 船橋洋一 改革の陣痛に立ちあって――『内部』の頃
5 毛里和子 同時代中国を見つめる眼――突き放しつつ、文化に逃げず
あとがき
関連年表
事項索引
人名索引
装幀=難波園子
本書を読まれる方へ
言説分析編
序 章 日本人の中国像の変遷――戦前、戦後、そして現代へ
一 日本人の中国像の解明――「市民外交」「国民世論」という視点から
二 「旧中国」から「新中国」へ
三 本書のねらいと時期区分
第一章 戦後日本人は文革の終わりをどう迎えたか 一九七三―七八年
――日中復交から平和条約締結まで
一 混迷する中国政治、足踏みする日中関係
二 脱文革・ポスト毛沢東の行方――批林批孔運動から第一次天安門事件へ
三 中米平和共存・中ソ対立・第三世界外交――「覇権条項」をめぐる国際情勢
四 台湾という視座
五 復縁から蜜月への兆し
第二章 友好と離反のはざまできしむ日中関係 一九七九―八七年
――中越戦争から民主化運動へ
一 高まる友好ムード、冷え込む論壇
二 視界不良の中ソ・中米関係
三 改革開放で露わになった中国の異質性
四 関心をひかなくなった中南海の政治動向
五 中国批判の根拠(一)――民主化を求める体制内外の声
六 中国批判の根拠(二)――香港からの情報と台湾からの世論工作
七 きしむ日中関係――対日「媚態外交」と対中「弱腰外交」
八 見失われてゆく紐帯の論理
第三章 天安門事件にいたる道 一九八八―九〇年
――日本から見た背景・経過・結末
一 日本からの天安門事件の眺め――当時と今と
二 事件の背景――五四運動の残響のなかで
三 事件の経過――愛国・民主から動乱・鎮圧へ
四 事件の結末――「国際的大気候」と「国内的小気候」
五 国家崩壊論と経済破綻論
第四章 天安門事件以後 反転する中国像 一九九一―九二年
一 経済制裁の継続か解除か
二 _小平最後の闘い――いかにV字回復はなされたか
三 浮足立つ香港、冷静保つ台湾
四 復交二〇年の日中関係修復から天皇訪中へ
五 天安門事件を背負って――中国の大国化と亡命者たち
六 反転する日中関係
第五章 戦後日本人の台湾像 一九四五年―現在
――対日情報・宣伝・世論工作との関連性をてがかりに
一 視界から消えた台湾
二 「以徳報怨」による道義外交の耐性
三 二度の台湾海峡危機――視界に入り始めた台湾および台湾人
四 日華断交――本格化する対日世論工作
五 日華関係から日台関係へ――対日世論工作の転換
六 形成されつつある対台湾認識経路
終 章 日本人の対中国認識経路を通して見た中国像
一 戦後―現代日本人の中国像 一九四五―九二年
二 同時代日本人の中国像 一九九〇年代―現在
三 対中認識経路をめぐる一〇のアスペクト
四 多彩な論者による豊かな中国像のために
補 章 戦後日本人のモンゴル像
――地政学的関心から文学的表象へ
一 戦前のモンゴル研究
二 敗戦によりフィールドを失ったモンゴル研究
三 異民族による中国征服王朝への関心
四 草原の非農耕騎馬遊牧民への郷愁
五 モンゴル独立への心情的加担
六 見失われたままの歴史的リアリティ
注
証言編
総解説 中国という巨大な客体を見すえて
1 若林正丈 歴史研究から同時代政治へ――台湾社会を見る目
2 西村成雄 変わりゆく中国に埋め込まれた歴史の地層を見据えて
3 濱下武志 地方・民間社会・南から見た中国の動態
4 船橋洋一 改革の陣痛に立ちあって――『内部』の頃
5 毛里和子 同時代中国を見つめる眼――突き放しつつ、文化に逃げず
あとがき
関連年表
事項索引
人名索引
装幀=難波園子